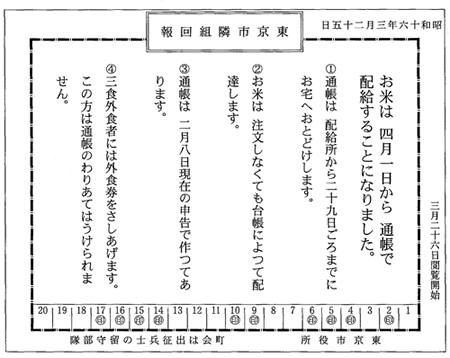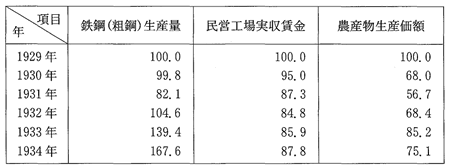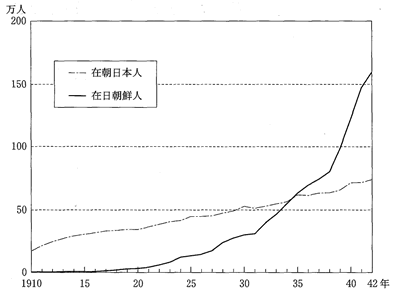2010年度 センター試験【日本史A】問題
(解答番号【1】~【34】)
第1問 ある高校生と先生との次の会話文を読み,下の問い(問1~3)に答えよ。(配点 8)
生徒:今回の主題学習では,東京駅と周辺の歴史について調べることにしました。
先生:どれくらい進んでいるのですか。
生徒:東京駅に関する主な出来事について,年表にまとめた程度です。
東京駅(現在の丸の内側の建物)は,日本銀行本店を設計したことでも知られる【ア】という建築家の設計によるもので,1914年に完成しましたが,1945年,空襲により大きな被害をうけました。2003年には重要文化財に指定され,現在,完成当初の状態に戻す復原工事が進められているところです。
先生:1921年には,
「平民宰相」とよばれた【イ】首相が駅頭で刺殺されるという事件もありましたよ。
1930年にも当時の首相が銃で撃たれています。
生徒:大きな事件の舞台にもなっているのですね。
先生:東京駅に関しては鉄道交通の発達との関係など,いろいろ重要な問題がありますが,他の駅にない特色として,国家の首都の玄関口としての性格があります。この図(
図1)は1903年にドイツ人技師が考えた設計案をもとに描いた絵で,平屋と2階建ての建物が連結する形になっています。
生徒:屋根は日本風のように見えます。
先生:面白いですね。でも最終的には,こちらの写真(
図2)のような「東洋一」といわれた長大な3階建ての駅舎が建てられました。これは(a)
列強の一員としてアジアに勢力を拡大しつつあった当時の日本の国威発揚の現れともいえます。そのへんにも注目して調べてみてください。
生徒:わかりました。このほか,東京駅が造られるころから,駅周辺に鉄道で通勤して働く人々の街ができ,(b)
新しい生活様式や文化が育っていく過程も調べてみたいと思います。

【写真1】(
図1)

【写真2】(
図2)
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】
(1) ア
岡倉天心 イ
原 敬
(2) ア 岡倉天心 イ
浜口雄幸
(3) ア 辰野金吾 イ 原 敬
(4) ア 辰野金吾 イ 浜口雄幸
問2 下線部(a)に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【2】
問3 下線部(b)に関連して,東京駅が完成した時期から第二次世界大戦までの間にみられた新しい文化の登場について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】
第2問 幕末から明治前期にかけての政治と社会に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 18)
A 開国後,幕末の政局のなかで幕府の権威は徐々に失われていった。1867年,土佐藩の建白をうけた15代将軍徳川慶喜は政権を朝廷に返上し,最終的に,
(a)戊辰戦争によって幕府勢力は崩壊した。
1869年,新政府は【ア】を行って旧藩主を知藩事に任じたが,1871年7月にはその知藩事も廃され,中央集権化が進められた。その後,幕府や藩の構成員であった武士も【イ】を廃止されるなどして,しだいに特権を失っていった。こうして幕藩体制は完全に解体し,新たな近代国家が成立していった。
一方,新政府を構成していったのは討幕派勢力を中心としたメンバーであったが,(b)
旧幕臣やその子であっても,各分野で活躍した人物が少なからず存在した。
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】
問2 下線部(a)について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】
問3 下線部(b)に関して述べた次の文X・Yと,それに該当する人物a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】
X 幕府の蕃書調所に勤め,明治に入ると明六社に参加して啓蒙活動を行った。
Y 幕臣の子として生まれ,アメリカ留学後,女子英学塾を創設した。
a
榎本武揚
b 西 周
c
岸田俊子
d
津田梅子
(1) X‐a Y‐c
(2) X‐a Y‐d
(3) X‐b Y‐c
(4) X‐b Y‐d
B 幕末期の政治的・経済的な変動は,民衆の意識にも大きな影響を与えていった。たとえば,伊予松山藩領の農民で宮大工も兼ねていた藤井
此蔵は,1864年の出来事として,「長州様は異人御打払の方
故,万人長州え随喜する。(中略)長州をほめる事
限なし」と,『藤井此蔵一生記』の中に書き留めており,(c)
攘夷を実行した長州藩を支持する民衆が多くいた様子がうかがえる。
また,幕末から明治前期においては,政治的・経済的な変動による社会不安や政治権力への不信感が高まり,(d)
大規模な騒動や一揆などが頻発した。一方,(e)
宗教をめぐっても大きな動きがあり,民衆の生活に影響をおよぼしたが,それによる混乱も各地で起こった。
問4 下線部(c)に関連して,幕末期の開国と攘夷をめぐる動向について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】
問5下線部(d)に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【8】
問6 下線部(e)に関連して,幕末から明治初期の宗教に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】
第3問 明治前期の産業・経済に関する次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 12)
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】
(1) ア 兌 換 イ デフレーション
(2) ア 兌 換 イ インフレーション
(3) ア 不 換 イ デフレーション
(4) ア 不 換 イ インフレーション
問2 下線部(a)に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】
(1) 内務省は,地方行政をつかさどった。
(2) 内務省は,警察行政を管轄した。
(3)
初代内務卿には,黒田清隆が就任した。
(4) 第二次世界大戦後,GHQの指令により内務省は解体された。
問3 下線部(b)に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】
問4 下線部(c)に関して述べた文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【13】
第4問
第一次世界大戦後から太平洋戦争後にかけての政治と社会に関する次の文章A・Bを読み,下の問(問1~5)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 15)
A (a)第一次世界大戦後,国際関係は比較的安定し,国内政治においては衆議院の多数政党が政権を担う政治のスタイルが定着していた。しかし,国際関係・国内政治はその後大きく変化していった。1930年代に入ると,国際関係の面では,満州事変の拡大により日本は国際的孤立を深めた。国内では政党内閣が崩壊した。また経済危機の影響があらわれ,深刻な社会問題が発生した。都市では失業者が増大し,農村では土地の取りあげなどに抵抗した農民による【ア】が多発した。一方,政治や経済の現状を批判し,労働者など無産階級の立場で変革を求める【イ】文学が興隆していたが,政府の弾圧が強まっていった。
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】
(1) ア
小作争議 イ
プロレタリア
(2) ア 小作争議 イ
自然主義
(3) ア 血税一揆 イ プロレタリア
(4) ア 血税一揆 イ 自然主義
問2 下線部(a)に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【15】
問3 下線部(b)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】
X この戦争は,日本軍が真珠湾の艦隊を攻撃した事件が,直接のきっかけとなって起こった。
Y この戦争が継続されるなか,日本は南方に進出するが,これに対してアメリカは石油の対日禁輸を行った。
(1) X 正 Y 正
(2) X 正 Y 誤
(3) X 誤 Y 正
(4) X 誤 Y 誤
問4 下線部(c)に関して,次の図は,日中戦争から太平洋戦争の時期に,当時の東京市の各家庭に回覧された
「東京市隣組回報」の一部を模式化したものである。これに関連して述べた文のa~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】
問5 下線部(d)に関連して,日中戦争,太平洋戦争の時期から戦後にかけての文化や教育について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】
(1) 日中戦争が始まると,政府は言論を統制するため,ニュース映画も含めてすべての映画の制作と上映を禁止した。
(2) 戦争が長期化するなかで,
日本文学報国会がつくられ,文学活動による戦争への協力が行われた。
(3) 太平洋戦争が始まると,小学校の制度が改められ,六・三制の義務教育が実施された。
(4) 敗戦後,占領軍が進駐すると,それまで使われていたすべての教科書は即座に廃棄され,民主主義的な教科書が使用された。
第5問 近代の経済界で活躍した渋沢栄一・敬三に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 23)
A 1840年に現在の埼玉県深谷市の豪農の家に生まれた渋沢栄一は,尊王攘夷運動に身を投じたのち,徳川御三卿の一つである一橋家に仕官し,その後幕臣となった。1867年のパリ万国博覧会の際には,徳川昭武に随行して西欧の経済諸制度への見識を深めた。その後(a)
大隈重信から強く要請されて大蔵省に入省し,【ア】の設立に尽力するなど,近代的金融制度の導入や財政的基盤の確立に取り組んだ。
栄一は大蔵省を辞した後も,
銀行業だけでなく【イ】の設立を指導するなど,(b)近代日本の産業の発達に貢献し,後年「日本近代産業の父」とよばれるようになった。政治への野心はほとんどみせず,(c)
帝国議会が設立されると貴族院議員に選出されたが,これを辞退し,民間人の立場を貫いた。
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】
(1) ア
三井銀行 イ
高島炭鉱
(2) ア 三井銀行 イ 大阪紡績会社
(3) ア 第一国立銀行 イ 高島炭鉱
(4) ア 第一国立銀行 イ 大阪紡績会社
問2 下線部(a)に関連して,明治時代の後半に成立した第1次大隈内閣について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】
問3 下線部(b)に関連して,日本の運輸・通信の近代化について述べた次の文X・Yと,それに該当する語句a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】
X おもに華族の出資により設立されたこの会社は,1891年に上野から青森までの路線を開通させた。
Y この人物の建議により,官営郵便制度が発足した。
a 日本国有鉄道
b 日本鉄道会社
c
森有礼
d
前島密
(1) X‐a Y‐c
(2) X‐a Y‐d
(3) X‐b Y‐c
(4) X‐b Y‐d
問4 下線部(c)に関連して,明治時代の議会制度成立の過程に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【22】
Ⅰ
西南戦争のさなか,立志社の片岡健吉らが,国会開設を求める建白書を提出した。
Ⅱ
選挙人資格を,直接国税15円以上を納入する満25歳以上の男性とする法律が制定された。
Ⅲ
明治十四年政変が起こり,国会開設の勅諭が発せられた。
(1) Ⅰ‐Ⅱ‐Ⅲ
(2) Ⅰ‐Ⅲ‐Ⅱ
(3) Ⅱ‐Ⅰ‐Ⅲ
(4) Ⅱ‐Ⅲ‐Ⅰ
(5) Ⅲ‐Ⅰ‐Ⅱ
(6) Ⅲ‐Ⅱ‐Ⅰ
B 晩年渋沢栄一は,(d)
第一次世界大戦のさなか,1916年に経済界から引退し,以後社会事業に尽力した。関東大震災の際には震災復興に貢献し,昭和恐慌のさなか,生活扶助などを内容とする救護法の実施に力を入れていたが,1931年に92歳で亡くなった。その後,(e)
日本は恐慌からの脱出を果たしつつも,戦争への道を歩むことになる。
栄一の孫である渋沢敬三は,大学卒業後,横浜正金銀行などを経て,太平洋戦争中に日本銀行総裁となり,終戦後には大蔵大臣をつとめた。一時は,公職追放の対象となったが,その解除後は国際電信電話株式会社の初代社長となるなど,(f)
高度経済成長下の日本で活躍した。祖父栄一は東京女学館の館長に就任するなど教育の発展に寄与したが,敬三も日本民族学協会を興してその会長に就任するなど,(g)
戦後日本における学術の発展に貢献した。
問5 下線部(d)に関連して,第一次世界大戦期における日本の政治・外交について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】
問6 下線部(e)に関連して,1929年から1934年にかけての日本経済の諸指数を示した次の表を参考に,当時の日本経済の特徴に関して述べた下の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】
日本経済の諸指数の推移
(いずれも1929年を100とする)
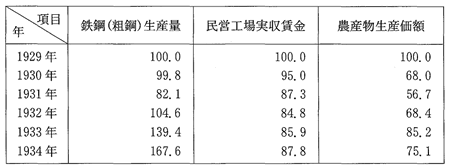
【表1】
(三和良一・原朗編『近現代日本経済史要覧』,中村政則『昭和の恐慌』より作成)
(注)農産物は,米・麦・繭・茶など。
a
満州事変の起こった年を境として,鉄鋼生産量は増加しはじめたが,民営工場の労働者の実収賃金はほとんど増加しなかった。
b 満州事変の起こった年を境として,鉄鋼生産量は増加しはじめ,民営工場の労働者の実収賃金も大幅な増加に転じた。
c 農産物生産価額の変化をみると,農民は
昭和恐慌の際に深刻な影響を受けたといえる。
d 農産物生産価額の変化をみると,農民は昭和恐慌の際にほとんど影響を受けなかったといえる。
(1) a・c
(2) a・d
(3) b・c
(4) b・d
問7 下線部(f)に関連して,戦後復興期から高度経済成長期の社会に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【25】
問8 下線部(g)に関連して,戦後における日本の文化・教育・学術に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】
第6問 近現代の日本では,多くの人々が海外へ渡るようになり,また,海外から日本に来る人々も増加した。こうした人の往来に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 24)
A (a)近代における日本人の海外移民は,19世紀後半に始まった。アメリカへの渡航者には,当初,働きながら学費を稼いで学ぶ苦学生も多かったが,1890年ころから,労働を主な目的として渡る日本人が増えていった。(b)欧米との不平等条約の改正を外交課題としていた日本政府には,単純労働者として渡米した日本人によって,日本の印象が悪くなるのではないかとの懸念もあった。
一方アジア方面へは,朝鮮への渡航者が明治前期から増えていった。(c)日朝修好条規による開港地には居留地が設けられ,日本人商人の活動がさかんになった。日本人商人による米や大豆の買い占めに対して,朝鮮側は防穀令を出すにいたり,外交問題となった。
問1 下線部(a)に関連して,近代日本の移民に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【27】
Ⅰ 日露戦争のころになると,アメリカ西海岸で日本人移民に対する排斥運動が高まった。
Ⅱ 日米修好通商条約の締結から10年後,アメリカ人の
斡旋)により,日本からハワイへの最初の移民が行われた。
Ⅲ
満州(中国東北部)への農業移民政策が大規模に展開された。
(1) Ⅰ‐Ⅱ‐Ⅲ
(2) Ⅰ‐Ⅲ‐Ⅱ
(3) Ⅱ‐Ⅰ‐Ⅲ
(4) Ⅱ‐Ⅲ‐Ⅰ
(5) Ⅲ‐Ⅰ‐Ⅱ
(6) Ⅲ‐Ⅱ‐Ⅰ
問2 下線部(b)に関して述べた次の文X・Yと,その当時の外務大臣a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】
問3 下線部(c)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】
X
江華島事件を契機に,日朝修好条規が締結された。
Y
日朝修好条規は,相互に領事裁判権を認めあう対等条約であった。
(1) X 正 Y 正
(2) X 正 Y 誤
(3) X 誤 Y 正
(4) X 誤 Y 誤
B 慶応義塾の創設者である【ア】は1885年に「我が日本の国土は亜細亜
の東辺に
在りと
雖も,その国民の精神は既に亜細亜の
固陋(注)を脱して西洋の文明に移りたり」と論じた。(d)
朝鮮からの留学生は慶応義塾が1881年に受け入れ始め,また中国から日本に来る留学生は日清戦争以後に急増した。
韓国併合後には日本の植民地支配を背景に(e)
日本内地に渡ってくる朝鮮人も増加し,朝鮮内外で朝鮮人による独立運動が展開された。なかでも第一次世界大戦後には,大規模な独立運動が起きた。この運動について,当時『東洋経済新報』記者で,第二次世界大戦後に首相にもなる【イ】は,「およそいかなる民族といえども,他民族の属国たることを愉快とする
如き事実は古来ほとんどない」と理解を示し,運動を弾圧した日本の対応に疑問を呈した。
(注)固陋:古い慣習や考えに固執すること
問4 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】
(1) ア
福沢諭吉 イ
石橋湛山
(2) ア 福沢諭吉 イ
寺内正毅
(3) ア 中江兆民 イ 石橋湛山
(4) ア 中江兆民 イ 寺内正毅
問5 下線部(d)に関して述べた次の文X・Yと,それに該当する人物名a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】
X 慶応義塾に留学生を送ったこの人物は,日本が行ったような近代化をめざして,1884年に朝鮮で政変を起こすが失敗し,日本に亡命した。
Y 1905年に東京で中国人留学生らと中国同盟会を結成したこの人物は,辛亥革命のなかで中華民国臨時大総統に就任した。
a
金玉均
b
安重根
c
孫文
d

(1) X‐a Y‐c
(2) X‐a Y‐d
(3) X‐b Y‐c
(4) X‐b Y‐d
問6 下線部(e)に関連して,次のグラフについて述べた文として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】
在朝日本人(朝鮮在住日本人)と在日朝鮮人(日本内地在住朝鮮人)の人数の推移
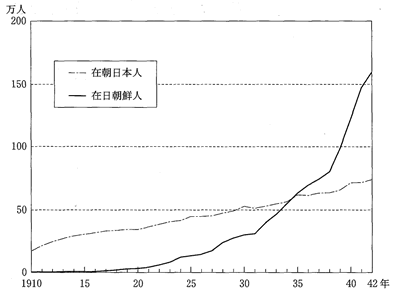
【グラフ1】
(『朝鮮総督府統計年報』『内務省警保局統計』より作成)
(1) 韓国併合時の在日朝鮮人数は在朝日本人数の3分の1ほどであった。
(2) 関東大震災が起こったとき,在日朝鮮人数は25万人に満たなかった。
(3) 在日朝鮮人数が在朝日本人数を上回るのは,盧溝橋事件以後である。
(4) 太平洋戦争が始まったとき,在日朝鮮人数は100万人に満たなかった。
C 北米では,低賃金で働き,異なった文化をもつ日本人の増加は,現地社会から反発や攻撃を招き,1908年以後,日本人労働者のアメリカ本土への新規渡航は困難になっていった。そのためブラジルなど南米への日本人移民が増えた。しかし,それ以上に増加したのはアジアへの移住である。さらに,(f)
太平洋戦争期には,日本政府や日本軍による人の動員や移動もいっそう拡大していった。
1945年の日本の敗戦にともない,アジア・太平洋地域の各地にいた日本の軍人や民間人など,600万人以上が日本に引き揚げることになった。一方で,(g)
敗戦前後の戦闘や混乱のなかで,引き揚げや帰郷がかなわなかった人々もいた。
問7 下線部(f)に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】
問8 下線部(g)に関連して,この時期の人の移動をめぐる動向について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】