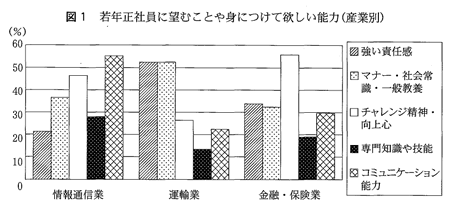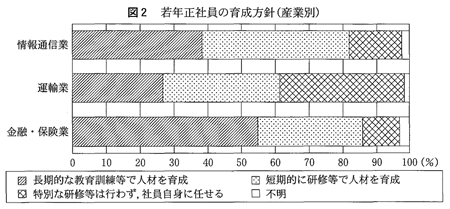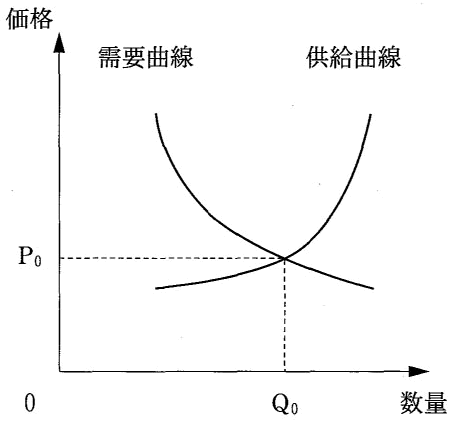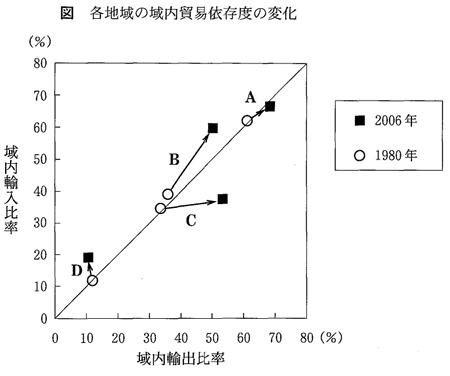2010年度 センター試験【現代社会】問題
(解答番号【1】~【36】)
第1問 二人の高校生(A,B)による次の会話文を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)
A:来週の日曜日,隣町との合併の是非を問う(a)住民投票が行われるけど,どっちに投票するつもりなの?
B:えっ,高校生に投票する資格があるの? それに,その日は田舎のおばあちゃんの所に(b)家族で出かける予定だから,投票には行けないよ。
A:前に先生が説明していたよ。市の条例では,満16歳以上に(c)投票資格が認められているって。それに,期日前投票もできるでしょ?
B:でも,合併でいったい何が変わるの? 住所表示くらいじゃないの?
A:それだけじゃないよ。例えば,多くの地方自治体が(d)財政上の問題を抱えているけれど,合併によって,自治体の行財政が効率的になるって言われているし……。
B:お金の無駄がなくなるんなら,反対する理由なんてないし,賛成するよ。
Aでも,市が大きくなると,住民の声が届きにくくなるとか,住民サービスの質が低下するおそれがあるとか,デメリットも指摘されているよ。
B:それは困るね。うーん,どっちがいいんだろう。
A:どっちにしても,(e)地域で取り組むべき問題は,自分たちの問題として捉えることが必要だと思うよ。住民が地方自治の主人公になることが ,民主主義の充実につながるんだよ。「地方自治は民主主義の学校」って言うでしょ。
B:そういえば,そんな言葉を現代社会の授業で習ったね。当日の予定はずらせないから,期日前投票に行ってみようかな。
問1 下線部(a)に関して,日本の地方自治体において
住民投票の実施が法律上必要な場合はどれか。最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】
(1) 有権者の50分の1以上の連署により,事務の監査が請求された場合
(2) 有権者の50分の1以上の連署により,条例の制定改廃が請求された場合
(3) 有権者の3分の1以上の連署により,議会の解散が請求された場合
(4) 有権者の3分の1以上の連署により,副市町村長の解職が請求された場合
問2 下線部(b)に関して,1980年代以降の日本の家族構成に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】
(1) 単独世帯(世帯人員が一人の世帯)の数が総世帯数に占める割合は,減少傾向にある。
(2) 三世代以上が同居する世帯の数が総世帯数に占める割合は,減少傾向にある。
(3) 世帯の平均人数は,増加傾向にある。
(4) 夫婦と子のみの世帯の数が総世帯数に占める割合は,増加傾向にある。
問3 下線部(c)に関連して,日本における参政権に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】
(1) 国民投票法上,憲法改正の国民投票の投票資格は,国政選挙の選挙権年齢が満18歳以上に改正されるまで,満20歳以上の国民に認められる。
(2) 被選挙権は,衆議院議員については満25歳以上,参議院議員については満30歳以上の国民に認められている。
(3) 最高裁判所は,外国人のうち永住者等に対して,地方選挙の選挙権を法律で付与することは,憲法上禁止されていないとしている。
(4) 衆議院議員選挙において,小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは,禁止されている。
問4 下線部(d)に関連して,日本の財政と税の状況に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】
(1) 地方自治体は,法律の範囲内で,条例によって課税することができる。
(2) 国債残高は,1990年代半ばから現在に至るまで,減少傾向にある。
(3) 現在,地方交付税が交付されている地方自治体の割合は,全国の地方自治体の3割程度である。
(4) 国家予算の成立には国会の議決を必要とし,予算案の審議については参議院が先議権を有する。
問5 下線部(e)の一例として,環境問題がある。日本の環境政策に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】
(1) 高度経済成長期には,環境アセスメント(環境影響評価)法が制定され,工業地帯で公害対策が進んだ。
(2) 資源の再生利用など,循環型社会の形成に向けた地域的取組みを促進するために,公害対策基本法が制定された。
(3) 企業には,住民による環境保全活動を支援することが,企業の社会的責任(CSR)の一環として,法律で義務づけられている。
(4) 国や地方自治体が環境負荷の少ない商品などを調達することが,グリーン購入法によって推進されている。
第2問 次の文章を読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点
22)
近年,(a)国境を越える人の移動が世界中でますます盛んになっている。
国境を越えて移動する人のなかには,(b)民族や(c)宗教の対立などにより祖国を離れざるを得ない(d)難民もいれば,より良い就労機会を求めて外国に向かう人々もいる。しかし,外国人の受入れに対しては,積極的な態度をとる国もある一方で,慎重な態度をとる国もある。
日本は,外国人を受け入れることに慎重な姿勢をとり続けてきたと言われる。(e) 労働者の受入れについても,日本はこれまで消極的であった。しかし,近年,フィリピンやインドネシアとの間で(f)EPA(経済連携協定)が締結され,看護・介護分野への外国人労働者の受入れが進みつつある。この動きの背景にあったのは,これらの分野における(g)人手不足である。だが,これには異論がなかったわけではない。例えば,労働環境の改善により人手不足の解決を図る方が先決だという指摘もあった。
外国人の受入れに慎重と言われる日本でも,実際には,200万人を超える外国人が様々な理由で生活しており,そうした(h)外国人の数は2007年までの10年間で1.5倍になるなど大きく増加してきた。それに伴い,一緒に来日する家族に対する教育や日本社会への適応の支援をどうするかといった問題も生じている。
国境を越える人の移動の増加という「グローバル」な現象が,「国内」の労働問題や教育問題にも大きな影響を及ぼす時代になった。我々は世界の動きにも目を向けつつ,人の移動がもつ多様な側面を理解した上で,今後,どのような社会を築いていくかを考える必要がある。
問1 下線部(a)に関して,国家の領域や主権に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】
(1) 国家は,「一定の領域」・「共通の言語」・「主権」をもっており,これは国家の三要素と呼ばれる。
(2) 月その他の天体を含む宇宙空間に対する領有権を国家が主張することは,条約上,できない。
(3) 現在では,いずれの国家の主権も及ばない地域は,地球上に存在していない。
(4) 国際連合(国連)憲章は,領土をめぐる国家間の紛争については,国際司法裁判所に付託することを紛争当事国に義務づけている。
問2 下線部(b)に関して,民族の対立・共存に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】
(1) イスラエルとパレスチナの対立は21世紀に入っても解消せず,ガザ地区などで武力紛争が起きた。
(2) 国連憲章は,人民の自決の原則をうたい,国内の少数民族が分離独立を求めた場合には,それを認めることを,加盟国に義務づけている。
(3) オーストラリアでは,「白豪主義」という,白人を優遇する移民政策が採られていたが,現在では廃止されている。
(4) 世界各地の民族紛争や地域紛争の解決に尽力したことが評価され,アハティサーリはノーベル平和賞を受賞した。
問3 下線部(c)に関して,いわゆる世界三大宗教の特徴に関する次の記述
ア~ウと,その宗教を信仰する人口が一国のなかで最も多数を占めるアジアの国名A~Cとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(6)のうちから一つ
選べ。【8】
ア 唯一神に服従し,信仰箇条である六信や信仰行為である五行を守ることの大切さを説く。
イ 唯一神を崇拝し,神の愛(アガペー)を自覚することや,神の愛を周囲の人に実践する隣人愛の大切さを説く。
ウ あらゆるものは相互依存しているととらえ,他者により生かされる自分を自覚することや,慈悲の心の大切さを説く。
A タイ B インドネシア C フィリピン
(1) ア-A イ-B ウ-C
(2) ア-A イ-C ウ-B
(3) ア-B イ-A ウ-C
(4) ア-B イ-C ウ-A
(5) ア-C イ-A ウ-B
(6) ア-C イ-B ウ-A
問4 下線部(d)に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)
のうちから一つ選べ。【9】
(1) 難民条約上,難民とは,大規模な自然災害や戦争・国内紛争のために国外に逃れた者を言う。
(2) 難民条約は,追害にさらされるおそれのある国に難民を追放・送還することを禁止している。
(3) 国連は,難民保護などを目的とする機関として,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)を設立した。
(4) 日本は,難民条約への加入に当たって,出入国管理及び難民認定法を定め,難民を認定する手続を整えた。
問5 下線部(e)に関連して,送出し国(外国に労働者を送り出す国)と受入れ国(外国人労働者を受け入れる国)に関する記述として適当でないもの を,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】
(1) 送出し国のなかには,医療など専門的な知識を持つ人々が外国へ移住したためにその分野の専門家が少なくなる,「頭脳流出」に悩んでいる国がある。
(2) 送出し国に家族を残して外国で働く人々の所得は,送出し国のGDP(国内総生産)に含まれる。
(3) 受入れ国のなかには,外国人労働者が自国民の就労機会を奪うなどの理由から,反移民運動が起こった国がある。
(4) 外国人労働者の受入れについては,原則的に,各国の裁量にゆだねられている。
(1) NAFTA(北米自由貿易協定)を形成するアメリカ・カナダ・メキシコの3か国は,共通の通貨を採用している。
(2) WTO(世界貿易機関)の無差別の原則に反することから,WTOは加盟国がFTAを締結することを認めていない。
(3) 日本の推進しているEPAは,投資ルールや知的財産制度の整備が含まれないなど,FTAよりも対象分野が限定されている。
(4) アメリカと中国は日本の貿易相手国上位2か国であるが,日本はいずれの国ともEPA・FTAを結んでいない。
問7 下線部(g)に関連して,日本の労働市場に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】
(「この設問は、2008年以前の状況に関するものである。」という「補足説明」が会場でなされた。)
(1) 男女雇用機会均等法の改正により,募集・採用における男女差別が禁止された結果,現在では,平均賃金の男女格差は解消している。
(2) 日本の労働組合は,雇用の流動化などの要因によって,その組織率をさらに低下させている。
(3) バブル崩壊後の不況によって,就業者数が減少したために,非正規労働者の数は1990年代全体を通じて減少した。
(4) 労働者派遣法の改正により,対象業務の範囲が見直され,あらゆる業務に対して労働者派遣を行うことが可能になった。
問8 下線部(h)に関して,日本に入国する外国人や日本で生活している外国人の現状に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】
(1) 日本は,入国する外国人に対して,指紋と顔写真を提供することを原則として義務づけていたが,現在ではこうした制度は廃止されている。
(2) 一国の労働力人口全体に占める外国人労働者の割合は,日本はアメリカよりも低かったが,バブル崩壊以後,外国人労働者の受入れが進んだ結果,アメリカよりも高くなった。
(3) 労働基準法には,不法就労をする外国人労働者は適用対象外であると明記されている。
(4) 日本人の父と外国人の母から生まれた子どもが,父母が婚姻をしていないことなどを理由に,日本国籍を取得できないとされた事例について,国籍法の規定が違憲であるという判決を最高裁判所が下した。
第3問 次の文章を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)
あなたはなぜ,大学で学ぼうとしているのだろうか。大学という(a)教育の場で学ぶことには,どのような意味があるのだろうか。
これまであなたは,与えられた課題を中心に勉強してきたかもしれない。しかし,大学では,自分の関心と知への欲求から学びが始まる。自然の不思議さに胸躍らせたり,芸術作品に心震わせたり,社会の問題に憤ったりしたことは,あなたにもあるだろう。それらはすべて,大学では学びにつながる。学んだ経験が
活きて,やりたいことが見つかったり,(b)自分の適性や能力に合う職に就いたりするようになるかもしれない。つまり,学ぶことはあなた自身のためになる。
しかし,学びは,個人的なことにとどまらず,社会的な意味をもちうる。あなたがふと抱いた疑問が,既成の学問や科学を見直す契機となり,知の創造や新たなアイディアの提案に至ることもある。多面的な見方や論理的な思考方法を身につけることで,物事の社会的意義や功罪などを的確に判断することが可能になる。仲間と対話し協働することを通して,問題に深く取り組むことも可能になる。
つまり,学ぶことは,社会をより良くすることにつながっており,(c)社会参加の第一歩でもある。
(d)人の生涯にわたる発達のなかで,学生時代にこそ可能なことがある。
試行錯誤や果敢な挑戦をしつつ,自分の生き方を考え,(e)キャリアを開発し,大いに学ぶことが,大学生には期待されているのである。
問1 下線部(a)に関連して,日本の
教育基本法に規定された,国及び地方公共団体の責務についての記述として
適当でないものを,次の(1)~(4)の
うちから一つ選べ。【14】
(1) 義務教育の機会を保障すること。
(2) 能力があるにもかかわらず,経済的理由によって修学が困難な者に対して,奨学の措置を講ずること。
(3) 幼児期の教育を無償で実施すること。
(4) 障がいのある者が,その障がいの状態に応じ,十分な教育を受けられるよう,教育上必要な支援を講ずること。
問2 下線部(b)に関連して,次の二つの図は,企業に対して行った若年正社員の能力や育成に関する調査結果の一部を示したものである。
図1は,
企業が「若年正社員に望むことや身につけて欲しい能力」について,
図2 は,企業の「若年正社員の育成方針」について,産業別に回答企業の割合を示している。これらの図から
読み取れることとして正しい記述を次のページのA~Cのなかからすべて選び,その組合せとして最も適当なものを,次のページの(1)~(8)のうちから一つ選べ。【15】
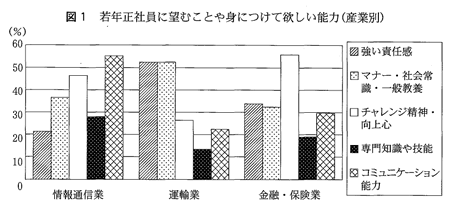
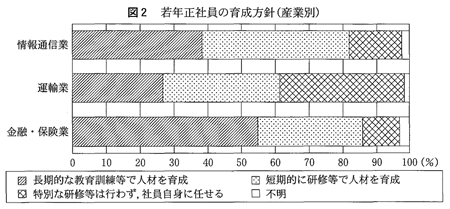
(注1)
図1は,12の選択肢から3つまで複数回答した結果について,特徴的な5つの選択肢の回等割合を示している。
(注2)
図2は,3つの選択肢から1つを回答した結果を示している。
(注3)
図1,
図2とも,厚生労働省「企業における若年者雇用実態調査:若年正社員を中心として」(平成17年10月調査)により作成。
A 「情報通信業」と「運輸業」では,望むことや身につけて欲しい能力で,上位2位までの回答は異なっているが,両産業とも育成方針では「特別な研修等は行わず,社員自身に任せる」と3割以上の企業が回答している。
B 望むことや身につけて欲しい能力では,5割以上の回答を得た三つの産業に共通する能力はなく,育成方針でも,それぞれの産業における回答割合の順位が異なっている。
C 「金融・保険業」では,望むことや身につけて欲しい能力として「強い責任感」と「専門知識や技能」をそれぞれ5割以上の企業が選択し,育成方針として「長期的な教育訓練等で人材を育成」と「短期的に研修等で人材を育成」を合計すると8割以上の企業が選択している。
(1) AとBとC
(2) AとB
(3) AとC
(4) BとC
(5) A
(6) B
(7) C
(8) 正しい記述はない
問3 下線部(c)に関連して,社会参加に関する事象や考え方についての記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】
(1) リースマンは,アンガジュマンの概念を示し,個人がある行為を選ぶことは,同時に人類全体のあり方を選ぶことであるとした。
(2) マザー・テレサは,愛と奉仕の精神に基づき,インドのコルカタ(カルカッタ)を拠点に,ハンセン病患者や貧困者などの救済に尽力した。
(3) 日本では,労働者はボランティア休暇を取得することが,労働基準法に明記されている。
(4) 障がいのある人もない人も共に生活する社会を目指すフェアトレードの考えに基づき,建物や製品にユニバーサルデザインが導入されている。
問4 下線部(d)に関して,人の発達に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】
(1) ハヴィガーストは,青年期の発達課題として,職業の選択と準備,大人からの情緒的独立,市民として必要な知識と態度の発達などを挙げた。
(2) エリクソンは,人間の一生についてライフサイクルの観点から論じ,乳児期から老年期までの諸段階の特徴を記述した。
(3) レヴィンは,青年を,子どもにも大人にも帰属せず,両者の境界に位置しているマージナルマンと呼んだ。
(4) ルソーは,青年が自己の価値観の確立に伴い,親の保護から自立することを 反動形成と呼んだ。
問5 下線部(e)に関して,次の文章中の【A】~【C】に入る語句の組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(8)のうちから一つ選べ。【18】
キャリアの開発とは,職場での技能習得や,昇進や転職等による地位向上だけではない。キャリアとは,職業生活を中核として,【A】築かれる経歴のことであり,余暇など,仕事以外の生活を【B】。高校や大学などの在学時に教育の一環として職場就労経験を得る【C】は,生徒や学生にとっては,職種や業務を理解し,自分の職業上の適性を把握し,働くことのイメージを形成する,貴重な機会である。そうした機会を利用して,将来に向けて自らのキャリアを考えていく必要がある。
(1) A-生涯にわたって B-含まない C-インターンシップ
(2) A-生涯にわたって B-含まない C-ワークシェアリング
(3) A-生涯にわたって B-含む C-インターンシップ
(4) A-生涯にわたって B-含む C-ワークシェアリング
(5) A-在籍期間に限って B-含まない C-インターンシップ
(6) A-在職期間に限って B-含まない C-ワークシェアリング
(7) A-在職期間に限って B-含む C-インターンシップ
(8) A-在職期間に限って B-含む C-ワークシェアリング。
第4問 次の文章を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)
人間の活動が(a)
地球環境への負荷を高める要因の一つとして,人間の活動に伴う資源消費の増大が挙げられる。人間による資源消費は,「一人あたりの資源消費」と「人口」という,二つの因子の積で
捉えることもできる。
このとき,資源消費の増大にどちらの因子がより大きく影響しているかは,開発途上国と先進国でそれぞれ異なる。
開発途上国における資源消費の増大は,(b)
人口の増加による影響が大きいと言われる。多くの開発途上国では,死亡率が低下している一方で,高い出生率が続いている。人口が増加すれば,たとえ一人あたりの資源消費が少ないままでも,人々の生活や産業を支える(c)
食糧や水,エネルギーなどの資源がさらに必要となる。
他方,先進国における資源消費は,一人あたりの資源消費の影響が大きいとされる。先進国のライフスタイルは大量消費型であり,例えば
OECD(経済協力開発機構)諸国の一人あたり一次エネルギー消費(石油換算)は,非OECD諸国の何倍にも及んでいるのである。人口については,先進国の多くで出生率が下がっており,(d)
少子化が問題となっている国もある。しかし,人口がさほど増加していなくても,一人あたりの資源消費が減少するようにライフスタイルが変化しなければ,資源消費に伴う環境への負荷は軽減しない。
このように,状況は異なるが,世界の国々は資源消費によって環境に負荷をかけており,その影響も一国内に限定されるものではない。資源消費を抑制し,
地球環境問題を解決するためにも,(e)
国際的な取組みを進めていくことが不可欠である。
問1 下線部(a)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】
(1) 日本は,かつて世界のなかで木材輸入量が最も多く,熱帯林減少の原因国とされていたが,今では国内の森林が増え輸出超過になっている。
(2) 生物の多様性の保全と持続可能な利用などを目的とする,生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)が採択された。
(3) オゾン層が破壊された結果,フロンが発生し,健康に悪影響を及ぼすことが,問題となっている。
(4) 水鳥の生息地として重要な湿地の保全と適正な利用に関するバーゼル条約が採択された。
問2 下線部(b)に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】
(1) 人口が増加している韓国では,現在,一組の夫婦に二人以上の子どもの出産を認めない人口抑制政策をとっている。
(2) 開発途上国における人口増加問題の背景には,子どもに家計の稼ぎ手としての役割を期待する考え方がありと指摘されている。
(3) 人口が増加している開発途上国のなかには,都市に人口が集中し,居住環境の悪化が問題となっている国がある。
(4) 森林破壊の一因として,開発途上国の人口増加による耕地拡大や薪・炭にするための木材の過剰伐採が指摘されている。
問3 下線部(c)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】
(1) 鶏などの家禽が鳥インフルエンザに感染した例は,開発途上国では見られるが,先進国では確認されていない。
(2) 国連食糧農業機関(FAO)は,栄養不足人口を減少させることなどを目標に掲げて,食糧問題に取り組んでいる。
(3) 遺伝子組み換え農作物を原材料とする加工食品について,遺伝子組み換え農作物が使われていることの表示を義務づける国はない。
(4) ハンガーマップ(飢餓マップ)において,栄養不足人口の割合が最も高い区分にランクづけられる国々は,南アメリカ大陸に最も集中している。
問4 下線部(d)に関して,日本の動向と対策に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】
(1) 子の養育や家族の介護を行う労働者に対して休業を認める育児・介護休業法は,男女の労働者を区別せずに適用される。
(2) 年齢別人口構成は,多産多死の「つぼ型(紡錘型)」から,少産少死の「富士山型(ピラミッド型)」へと移行してきた。
(3) 子育てに対する社会的支援の充実などを図るために,ゴールドプランが策定された。
(4) 合計特殊出生率は,現在の人口を維持するのに必要とされる水準にまで回復している。
問5 下線部(e)に関する記述として最も適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】
(1) 国連環境計画(UNEP)は,ストックホルムで開催された「国連人間環境会議」の合意を受けて設立された国連機関である。
(2) 国連人口基金(UNEPA)は,人口問題という切り口から開発途上国を支援している。
(3) 日本では国際協力機構(JICA)が,開発途上国に対する技術協力のために開発途上国からの研修生を受け入れている。
(4) アジェンダ21は,ヨハネスブルクで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で採択されたものである。
第5問 次の文章を読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 22)
現在,
食品偽装や
悪質商法などをめぐって(a)
企業と消費者の間に様々なトラブルが発生している。(b)
企業と消費者との間にある情報の質や量,交渉力などの格差がその一因である。消費者は,(c)
市場における取引に必要な情報を十分に持たなかったり,他の選択肢がなかったりする状況で特定の取引を行ってしまうことがしばしばある。その結果,望まないものや安全でないものを購入してしまうことがある。
消費者は,こうしたトラブルの解決に向けて企業と交渉することが必要である。だが,そのような当事者の努力によってもトラブルが解決されなかったり,類似のトラブルが頻発したりするような場合,社会的な対応も求められる。そこにはいかなる主体がかかわり得るだろうか。以下のようなケースが考えられる。
まず,国などの公的機関が主導して,(d)
消費者の利益を保護するルール を作り,消費者保護の仕組みを整えることがあり得る。1968年制定の消費者保護基本法や1994年制定の
製造物責任法(PL法)はその好例である。また,第三者である民間機関が,消費者全体の(e)
利益の実現のために情報収集やトラブル防止の活動などをすることもあり得る。消費者契約法は,国の認定した消費者団体に,企業の不当な行為をやめさせるよう(f)
裁判を起こすことを認めている。さらに,マスメディアがトラブルの実態を広く知らせることもあり得る。これは,トラブルの早期発見・解決だけでなく,トラブルの未然防止のための政策づくりに向けた(g)
世論の形成にも有効である。
このように,企業と消費者との間で発生するトラブルの解決と防止に向けては,取引の当事者だけに任せるのではなく,社会的な対応も行うことが重要である。
問1 下線部(a)に関して,日本の消費者問題に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】
(1) 街頭などで通行人を呼び止め,営業所などに同行させて契約を迫る,いわゆるキャッチセールスが問題となっている。
(2) 人々を,一定の場所に集め,その場を盛り上げるなどして冷静な判断を失わせてから高額商品を買わせるクーリングオフが問題となっている。
(3) 薬害エイズ事件が契機となって,その原因となったキノホルムの販売中止措置が採られた。
(4) 豚肉を牛肉と偽るなど,食肉加工卸会社が行った一連の偽装事件が契機となって,食育基本法が制定された。
問2 下線部(b)に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】
(1) 中小企業の競争力向上を目指して,日本では現在,会社法によって,株式会社の最低資本金制度が設けられている。
(2) 企業が事業の再構築を行うことをリストラクチャリングというが,日本ではリストラという語で人員整理のことを意味する場合が多い。
(3) 企業が行うフィランソロピーとは,慈善活動・社会貢献活動のことであり,
福祉,地域興し,災害救援などの活動を支援することが含まれる。
(4) 他企業があまり進出していない隙間分野を開拓し埋めるビジネスとして,ニッチ産業が注目されている。
問3 下線部(c)に関連して,ある商品の市場において,需要・供給と価格の間に次の図のような関係が成り立っており,価格がP
0,取引量がQ
0にあるときに需要と供給は釣り合っており均衝状態にある。
いま,その商品の人気がなくなったため需要曲線が移動したとする。これ以外には条件の変化はないものとする。
このとき,新たな均衝状態に達したときの
価格と取引量の変化の記述として最も適当なものを,次の
(1)~(8)のうちから一つ選べ。【26】
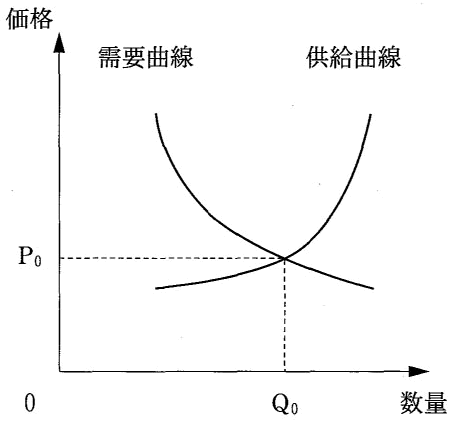
(1) 価格は上昇し,取引量は減少する。
(2) 価格は低下し,取引量は減少する。
(3) 価格は上昇し,取引量は増加する。
(4) 価格は低下し,取引量は増加する。
(5) 価格は上昇し,取引量の変化はいずれともいえない。
(6) 価格は低下し,取引量の変化はいずれともいえない。
(7) 価格の変化はいずれともいえず,取引量は減少する。
(8) 価格の変化はいずれともいえず,取引量は増加する。
問4 下線部(d)に関して,社会的に不利な立場におかれた人々の保護や支援に関する日本の法律や制度についての記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】
(1) 消費者保護基本法の制定を受けて,地方自治体は,消費者相談や消費生活の情報提供などを行う消費生活センター(消費者センター)を設置した。
(2) 犯罪被害者等の権利実現のため,犯罪被害者等基本法において,加害者に対する刑罰強化が定められた。
(3) 消費者から苦情を受けた場合,製造会社等は自社の製品の品質を速やかに調査する義務を負うと定めたPL法が制定された。
(4) 高齢者の尊厳保持のため,高齢者虐待防止法に基づき,高齢者介護のための介護保険制度が導入された。
問5 下線部(e)に関連して,現在の日本において,人々の利益の実現のために行われる労働や社会保障に関する法律・政策についての記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】
(1) 国民所得に占める社会保障給付費の割合は,先進諸国のなかで最も高い。
(2) 非正規労働者には,法律上,労働組合を組織し,団結する権利が認められていない。
(3) 労働争議において,自主的解決が難しい場合に,労働委員会が斡旋や仲裁などを図ることがある。
(4) 国の歳出予算において,生活保護費は社会保険費を上回っている。
問6 下線部(f)に関して,日本の裁判制度についての説明として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】
(1) 刑事裁判において有罪判決を受けた者を,さらに民事裁判で責任追及することは,憲法上許されない。
(2) すべての裁判官は,弾劾裁判所の裁判により罷免の判決を受けない限り,罷免されることはない。
(3) 民事裁判において,被告が理由なく裁判を欠席した場合,公務執行妨害罪に問われる可能性がある。
(4) 裁判員制度の対象となる事件は,公判の審理を継続的,計画的,迅速に行うために,公判前整理手続に付される。
問7 下線部(g)に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】
(1) 世論をより良く政治に反映させるため,日本では,国政選挙の候補者による 選挙運動期間中の戸別訪問が,法律上,認められている。
(2) 著名なジャーナリストや評論家のように,世論の形成に大きな影響力を持つ人は,オピニオン・リーダーと呼ばれる。
(3) 世論調査では,同じ調査項目であっても,質問の仕方などが変わると調査結果が異なることがある。
(4) 行政機関が命令等を制定しようとするときに,あらかじめ原案を示し広く公に意見を求める手続は,パブリックコメント(意見公募)手続と呼ばれる。
問8 本文では消費者問題に対する,当事者以外による社会的な対応について三つのケースが挙げられていた。近年の日本における代表的な消費者問題として,「銀行,消費者金融会社,クレジットカード会社などからの多額の借金を抱えて返済できなくなること」がある。この問題への対応として本文の三つのケースに該当しないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】
(1) 国が,地方自治体に,問題を抱える借り手側にどう対応したらよいかを示した相談の手引きを配布する。
(2) 新聞が,この問題に関する特集を組み,具体例,問題発生の仕組み,問題解決の方法などを紹介する。
(3) 借り手側である消費者が,収支のバランスをチェックするなどして,無駄な支出をと借り過ぎを抑えるようにする。
(4) 国の認定した消費者団体が,貸し手側である企業に対し,消費者の利益を不当に害する契約条項に関して,差止請求の裁判を起こす。
第6問 次の文章を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)
経済のグローバル化が進み,近年ますますカネやモノの移動が活発になってきた。発展途上国のなかには,この(a)
経済のグローバル化の恩恵を受けて経済発展を遂げてきた国もある。例えば,中国やインドは外国から資本や技術を積極的に受け入れて経済成長している。
アジアNIES(新興工業経済地域)も貿易取引を中心に産業構造の高度化を図った結果,一人あたりの国民所得が日本に並ぶ国も出てきた。
しかし,経済のグローバル化は弊害も招き得る。米国の
サブプライムローン問題を引き金として発生した世界的な経済危機は,グローバル化に伴う複雑な相互 依存関係の深まりが引き起こす問題の深刻さを如実に物語っている。(b)
1990年代後半に生じたアジア通貨危機も,グローバル化によって引き起こされた危機の一つだった。タイや韓国,インドネシアは外国から短期資本を受け入れることによって急速な経済成長を遂げていたが,いったん歯車が資本流出へと逆転してしまうと,急激な経済の悪化に直面した。こうした国々は,IMF(国際通貨基金)などの(c)
国際機関から金融支援を受けたが,経済の立ち直りには相当の努力と時間を要した。また,資本取引だけでなく貿易取引に関する交渉においても,相手国の市場開放を求める国と,自国の産業を保護したい国との間で対立が起きる場合もある。カネやモノを通じて(d)
国家間の相互依存関係が深まる以上,摩擦は生じ得る。
世界的な金融・経済危機に立ち向かう上で,経済のグローバル化が持つ功罪を踏まえ,弊害を和らげる努力がこれまで以上に求められている。そのためには,各国政府や国際機関,さらにNGO(非政府組織)などが,資金や技術,人材育成の面で一層協力することが必要であろう。そのなかで,(e)
日本が貢献できることは少なくないはずである。
問1 下線部(a)に関連して,1980年代以降,日本や他のアジア地域の国々が経験した経済のグローバル化や,それに伴う経済発展の状況に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】
(1) ASEAN(東南アジア諸国連合)の国々は,国内市場向けの製造業育成を中心とした政策により,経済発展を図ってきた。
(2) 米国に対する貿易黒字を拡大させていた日本は,貿易摩擦を回避するため米国での生産拠点から撤退した。
(3) 日本に続いてアジアNIESが,その後に続いてタイやマレーシアなどの国々が,経済発展をしてきた。
(4) フィリピンは,ドイモイと呼ばれる政策を採り,外資導入を積極的に推進した。
問2 下線部(b)に関して,
アジア通貨危機発生前後の状況を説明した記述として
適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】
(1) 危機当時,為替相場の変動を利用して,巨額の利益を上げたヘッジファンドがあった。
(2) 危機前には,大量に流出していた資金が,株式市場や債券市場の過熱化を引き起こしていた。
(3) 危機後,自国通貨の下落により,原料や部品調達を輸入に頼っている企業はコストを抑えることができ,経営の立ち直りは早かった。
(4) 危機後,ASEAN+3(日本・中国・韓国)では,同様の危機が起きた場合に備え,金融面で協力し合う体制が整えられた。
問3 下線部(c)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】
(1) UNDP(国連開発計画)は,開発援助の新たな指標として,出生時平均余命や識字率などを加味して算出されたHDI(人間開発指数)を導入した。
(2) UNCTAD(国連貿易開発会議)は,先進国間に存在する経済格差を,貿易を通じて解消することを目的として設立された。
(3) IBRD(国際復興開発銀行)は,第二次世界大戦後,加盟国の復興・開発支援を行ったが,日本は加盟後もその支援を受けずに経済発展を遂げた。
(4) IMFは,米国がドルと金との交換を停止したニクソン-ショックを契機として,国際収支の赤字国に融資を行うため設立された。
問4 下線部(d)に関連して,次の
図は,経済連携強化を図っている四つの地域について,その
域内貿易依存度(域内輸出比率と域内輸入比率)を,1980年と2006年とで比較し,その間の変化を矢印で示したものである。また,次ページの四つの記述は,
図についての説明である。これらを参考にして,
図の中の矢印A~Dと次ページの地域
ア~エの組合せとして最も適当なものを,次ページの(1)~(8)のうちから一つ選べ。なお,域内輸出比率とは,各地域の総輸出額に占める域内輸出額の割合,域内輸入比率とは,各地域の総輸入額に占める域内輸入額の割合である。【35】
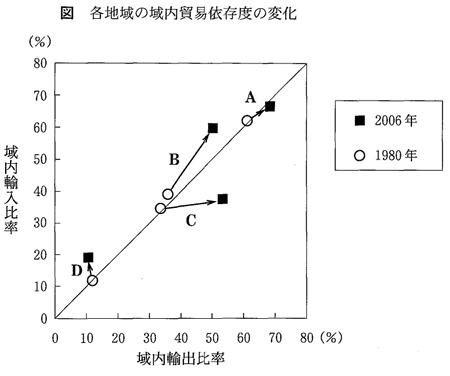
(注1)
1980年のデータは,EUについては2005年時点でのEU加盟国25か国について合算したものであり,ASEAN+3,NAFTA,MERCOSURについては2006年時点でのそれぞれの加盟国について合算したもの。なお,ASEAN+3には,台湾と香港の実績も含む。
(注2) 日本貿易振興機構「世界貿易マトリクス」により作成。
・ MERCOSUR(南米南部共同市場)は,1980年と2006年で域内貿易依存度の変化が少ない。
・ EU(欧州連合)はもともと域内貿易依存度が高く,輸出,輸入とも同水準の高さである。
・ ASESN+3とNAFTA(北米自由貿易協定)は1980年りも2006年で域内貿易依存度が大きく高まっているが,輸出と輸入のどちらでより高まっているかという点で異なる。
・ ASEAN+3の域内貿易依存度が輸入の方で高まっているのは,域内で部品を調達し完成品を域外に輸出する貿易形態がより進んだからだと推測される。
ア ASEAN+3
イ NAFTA
ウ EU
エ MERCOSUR
(1) A-ウ B-エ C-イ D-ア
(2) A-ア B-ウ C-エ D-イ
(3) A-イ B-ア C-ウ D-エ
(4) A-エ B-ウ C-ア D-イ
(5) A-ウ B-ア C-イ D-エ
(6) A-イ B-エ C-ア D-ウ
(7) A-ウ B-イ C-ア D-エ
(8) A-エ B-ウ C-イ D-ア
問5 下線部(e)に関連して,
日本のODA(政府開発援助)に関する記述として
適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】
(1) ODA総額に占める借款の割合は,DAC(開発援助委員会)加盟国の平均を下回る。
(2) ODAでは様々な地域が援助対象となっているが,ODA大綱はアジアを重点地域として位置づけている。
(3) ODA総額に占める道路や電力など経済基盤整備への援助割合は,DAC加盟国のなかで一位,二位を争う高さである。
(4) ODA大綱では平和の構築が重点課題として位置づけられており,紛争の再発防止のための支援なども行われている。