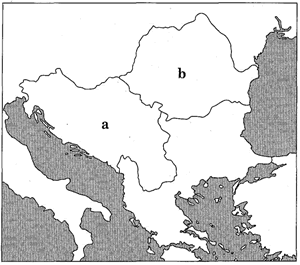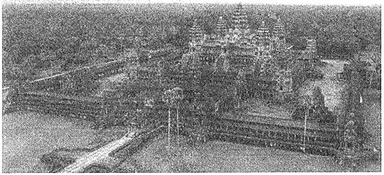2009年度 センター試験【世界史B】問題
(解答番号【1】~【36】)
第1問 人類が営む生業と労働は,経済・社会・政治の動きと密接にかかわりながら,大きく変容してきた。生業と労働の歴史について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)
A 清の学者趙翼は,明代の文化人の趨勢を論じて,(1)唐宋以来,文化・芸術に秀でた者の多くは科挙の合格者であったが,(2)明代になってその担い手は在野の人物に移っていったと述べている。明代中期の画家唐寅は,まさにその過渡期の人物と言える。彼は科挙で優秀な成績を収めながらも,不運な事件に巻き込まれ,栄達の道を絶たれてからは,蘇州で画業をなりわいとしながら自由奔放な生活を送った。明代中期から後期にかけて,在野の芸術家や文筆家が続々と現れたのは,(3)江南を中心とする商工業の発展によって都市の文化が成熟し,絵画や出版物が広く商品としての価値を持つようになったからであった。
問1 下線部(1)に関連して,次に挙げる人物は,いずれも唐代から宋代にかけての科挙の合格者である。それぞれの人物について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】
(1) 欧陽脩や蘇軾は,唐代を代表する文筆家である。
(2) 顔真卿は,宋代を代表する書家である。
(3) 宋の
王安石は,新法と呼ばれる改革を行った。
(4) 秦檜は,元との関係をめぐり主戦派と対立した。
問2 下線部(2)の時代に起こった出来事について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】
問3 下線部(3)について述べた次の文章中の【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】
明代中期から,長江下流域では絹織物や綿織物などの手工業が発展する一方,穀倉地帯は長江中流域に広がり,「【ア】熟すれば天下足る」という言葉が生まれた。山西商人や新安商人が活躍し,各地の都市に互助組織である会館や【イ】が置かれた。
(1) ア―
湖 広 イ―公 所
(2) ア―湖 広
イ―
租 界
(3) ア―蘇湖(江浙)
イ―
公 所
(4) ア―
蘇湖(江浙) イ―租 界
B アルプス以北のヨーロッパでは,(4)農民や都市の下層民が,一つの生業で生活を維持するのが困難であることも珍しくなかった。とりわけ,(5)15世紀後半から16世紀後半には,人口増加の影響もあって,大量の貧農や困窮した下層民が生み出され,(6)彼らの中には,傭兵
の道を選ぶ者も少なくなかった。徴募時の一時金や給与は,彼らの生活を支えた。三十年戦争は,こうした傭兵たちを主な担い手とした戦争だったのである。
問4 下線部(4)に関連して,農村や都市について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】
問5 下線部(5)の時期に起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】
問6 下線部(6)に関連して,兵制や兵士について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】
(1) ポエニ戦争後,
重装歩兵として従軍した農民層は経済的に豊かになった。
(2) 八旗は,順治帝が創設した軍隊である。
(3) イェニチェリは,オスマン帝国の常備軍であった。
(4) フランク王国では,
テマ制(軍管区制)の下で屯田兵制が行われた。
C 「鉄鋼王」と呼ばれたアンドルー=カーネギーは,近代における生業と労働の変容とともに人生を歩んだ人物である。彼は,1848年,家族に連れられ,スコットランドからアメリカ合衆国に移住した。その背景は,(7)工場製の安価な綿織物の普及により,家業の毛織物業が苦境に陥ったことにあった。鉄道の電信技師として働いた後,彼は実業家へと転じ,新技術を活用した鉄鋼業で成功を収めた。この時期の(8)大規模な産業構造の転換は,職人や農民から工場労働者へと転じる人々の急増,ホワイトカラーの出現など,生業と労働のあり方を大きく変容させた。また,(9)労働問題の深刻化もその帰結の一つであった。カーネギーの製鉄会社でも,生産の拡大とともに労働争議が頻発したのである。
問7 下線部(7)に関連して,イギリスの商業・製造業にかかわる出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】
(1) イギリスは,
マカートニーを派遣して清に自由貿易を認めさせた。
(2) イギリスでは,機械を打ち壊す
ラダイト運動が起こった。
(3) 茶法の廃止をきっかけに,イギリスの北米植民地で,
ボストン茶会事件が起こった。
(4) ナポレオンは,イギリスとアメリカ合衆国の間の通商を断絶させるために,
大陸封鎖令を出した。
問8 下線部(8)に関連して,アメリカ合衆国の産業・経済について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】
問9 下線部(9)に対する各国ないし国際機関の取り組みについて述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】
第2問 学校のあり方は,時代と地域によって様々に異なった。世界史における学校・教育に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。
(配点 25)
A ヨーロッパ世界では,学校教育は古代ギリシア以来の伝統を持っている。プラトンが開いた学園であるアカデメイアは,【ア】の皇帝(1)ユスティニアヌスによって6世紀に異教の温床として閉鎖されるまで,約900年間存続した。中世になると,今日のヨーロッパの大学の原型が出現している。イスラーム世界では,【イ】と呼ばれる機関で法学を中心とした教育が行われた。イスラーム世界の文化は,中世のヨーロッパに大きな影響を与え,(2)12世紀ルネサンスの源の一つとなった。
問1 文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】
問2 下線部(1)の人物について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】
問3 下線部(2)に関連して,12世紀に起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】
B 10世紀以降における中国の学校は,(3)科挙の受験に備えるものが多く,学問も儒教が重んじられた。16世紀に,(4)イエズス会の宣教師が西洋の学問を伝えたが,西洋の学問が儒教に代わって主流となることはなかった。19世紀の洋務運動以降の諸改革の中で,西洋の科学技術や学問に関心が集まり,学堂と称する新式の学校が設立された。また,1870年代より海外への留学生派遣も始まった。1919年には,フランスで働きながら学ぶ勤工倹学が始まり,後に中国共産党の指導者となる(5)周恩来などが渡仏した。
問4 下線部(3)に関連して,中国と朝鮮の官吏登用制度について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】
(1) 殷は,
郷挙里選により管理を登用した。
(2) 三国時代の呉は,
九品中正(九品官人法)を始めた。
(3) 元は,
殿試を始め,皇帝の独裁体制を強化した。
(4) 高麗は,科挙を採用した。
問5 下線部(4)に関連して,中国におけるキリスト教布教や宣教師の活動について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】
問6 下線部(5)の人物について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】
C (6)学校教育で使われる歴史教科書は,記述の内容により,他国民に対する一面的な見方を作り出す可能性がある。このような問題の解決に向けて,第一次世界大戦後の⑦北欧諸国では,出版前の教科書を隣国の歴史家が検討する制度が作られた。第二次世界大戦後には,歴史教育をめぐる多国間の対話が進んだ。近年の試みの一つとしては,以前に(8)ユーゴスラヴィアを構成していた諸国をはじめ,バルカン半島とその周辺の国々の専門家が協力して,共通歴史副教材を作ったことが挙げられる。
問7 下線部(6)に関連して,学校や教育に関する歴史について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】
a イギリスでは,19世紀後半,
教育法(初等教育法)が制定された。
b
アズハル学院は,ファーティマ朝時代のカイロに設立された。
(1) a―正 b―正
(2) a―正 b―誤
(3) a―誤 b―正
(4) a―誤 b―誤
問8 下線部(7)に関連して,アイスランド・スウェーデン・デンマーク・ノルウェーの歴史について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】
(1) ノルマン人は,原住地であるアイスランドから,ノルウェーに進出した。
(2) デンマークには,16世紀,ルター派が広まった。
(3) ノルウェーは,ウィーン会議により,独立を認められた。
(4) スウェーデンは,第二次世界大戦中,ドイツに占領された。
問9 下線部(8)の国について述べた次の文アまたはイと,1991年に解体が始まる前のこの国の位置を示す下の地図中のaまたはbとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】
第3問 信仰や宗教は,個人の思考や行動のみでなく,社会のあり方にも大きな影響を与えてきた。信仰や宗教について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)
A 古くから人々は,大空の星に特別な力を認めたり,太陽や月を神と崇めたりする(1)信仰を抱いてきた。東北アジア地域でも,広く太陽への信仰が存在する。また,漢字が使われるようになると,信仰対象や神話が「天」という中国的な表現を借りて言い表されることもあった。中国の『三国志』に,(2)高句麗では「十月に天を祭る」と記され,鴨緑江の中流北岸に立つ高句麗の広開土王碑に,その始祖は「天帝の子で,母は河伯(黄河の神)の娘である」とある。この高句麗の始祖,すなわち伝説上の(3)建国者期が,北魏について記した『魏書』に見える朱蒙に当たるとされている。
問1 下線部(1)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】
問2 下線部(2)の国について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】
(1) 4世紀に,
楽浪郡を滅ぼした。
(2) 5世紀に,百済や
新羅と対立した。
(3) 6世紀に,
百済を滅ぼした。
(4) 7世紀に,
唐と戦った。
問3 下線部(3)に関連して,歴史上の建国者について述べた文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】
a
劉邦は,項羽を破り,長安を都とした。
b
耶律大石は,西遼(カラ=キタイ)を建てた。
(1) a―正 b―正
(2) a―正 b―誤
(3) a―誤 b―正
(4) a―誤 b―誤
B (4)東南アジアの信仰は,重層的であると説明されることがある。すなわち,もともと存在していた精霊信仰の上に,他地域から伝播したヒンドゥー教や仏教,(5)イスラーム教,キリスト教が受容されていったというのである。現在においても,東南アジアの多くの地域では,精霊信仰を取り込んだ様々な宗教が信仰されている様子を見ることができる。このような信仰の重層性は,それぞれ受容した宗教は異なるが,(6)オセアニア地域などにおいても観察することができる。
問4 下線部(4)の地域における遺物や遺跡を示した次の写真aとbについて述べた下の文アとイの正誤の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】
 |
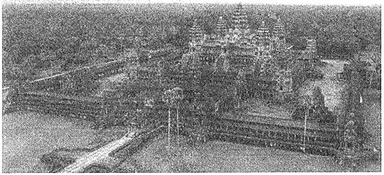 |
| a |
b |
ア aの遺物は,
ドンソン文化を代表する器物である。
イ bの遺跡は,
大乗仏教寺院として建造されたものである。
(1) ア―正
イ―正
(2) ア―正
イ―誤
(3) ア―誤
イ―正
(4) ア―誤
イ―誤
問5 下線部(5)の宗教とその文化の広がりについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】
(1) 7世紀に,ベルベル人が建てた
ムラービト朝は,イスラーム王朝であった。
(2) 11世紀に,
マラッカ王国の王がイスラーム教に改宗した。
(3) イル=ハン国は,
フラグの治世にイスラーム教を国教とした。
(4) 東アフリカでは,イスラーム文化の影響を受けて
スワヒリ文化が生まれた。
問6 下線部(6)の地域で起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】
(1) クックが,18世紀にオセアニアを探検した。
(2) イギリス領となったオーストラリアでは,先住民
マオリ人が土地を奪われた。
(3) スペイン領であった
ハワイは,アメリカ合衆国に併合された。
(4) ミッドウェー海戦では,日本軍がアメリカ軍に壊滅的な打撃を与えた。
C 中世ヨーロッパに生きた人々は,(7)死後に天国に入ることを強く願っていた。(8)カロリング朝フランク王国時代には,ローマ=カトリック教会は,死後の救済のために,宗教的な罪の浄化の必要を説いた。こうして,自分の罪を認めて懺悔ざんげし,それを償うという贖罪しょくざいの慣行が広まり,また,(9)修道院を中心にして生者が死者の昇天を祈ることが求められるようになった。このような贖罪と祈りの要求は,次第に増大していった。これに対し,宗教改革では,罪の許しを与えるとされた贖宥状(免罪符)の販売が批判され,霊魂の救済は信仰のみによることが主張された。
問7 下線部(7)に関連して,死後の世界や墓地について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】
(1) 古代エジプト人は,
オシリスによって死者が審判を受けると信じていた。
(2) 古代ローマの
カタコンベは,キリスト教の国教化とともに造られ始めた。
(3) イスラーム教は,
輪廻からの解脱を説いた。
(4) 中世末にヨーロッパで描かれた
「死の舞踏」は,最後の審判の様子を示している。
問8 下線部(8)の王国が建国された8世紀に起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】
問9 下線部(9)について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】
a
クリュニー修道院で,教会改革運動が起こった。
b
ヘンリ8世は,修道院を解散し,その財産を没収した。
(1) a―正 b―正
(2) a―正 b―誤
(3) a―誤 b―正
(4) a―誤 b―誤
第4問 人々の移動と移住は,世界史を通じてしばしば見られる現象であり,政治・経済・社会・文化に大きな影響を与えてきた。移動と移住について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)
A ラテンアメリカの歴史は,移住の歴史でもあった。(1)後にインディオと呼ばれた先住民もまた,氷河時代にアジア大陸からベーリング海峡経由でアメリカ大陸に移動し,各地の環境に適応しながら南下した人々であった。大航海時代以降,ラテンアメリカには,(2)スペイン人やポルトガル人らが征服者や植民者として渡来したほか,(3)アフリカから多数の人々が,強制的に移住させられた。さらに19世紀から20世紀初頭の「移民の世紀」には,国際的な労働力の移動が本格化し,ラテンアメリカ諸国,とりわけブラジルやアルゼンチンなどに,ヨーロッパやアジアから数多くの移民が到着した。
問1 下線部(1)に関連して,アメリカ大陸の先住民の諸文明について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】
問2 下線部(2)に関連して,イベリア半島の歴史について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】
(1) ポルトガルは12世紀,神聖ローマ帝国から独立した。
(2) スペイン国王
カルロス1世は,ポルトガル王を兼ねた。
(3) スペインの作家
セルバンテスが,『ドン=キホーテ』を著した。
(4) グラナダに,ロココ様式を代表する
アルハンブラ宮殿が建設された。
問3 下線部(3)の地域について述べた文として波線部の誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】
(1) 
,
鄭和の遠征艦隊の一部はアフリカ東岸に到達した。
(2) 19世紀,
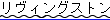
はアフリカ内陸部の探検を行った。
(3) リベリアは

に独立し,共和国となった。
(4) アンゴラは1970年代に,

から独立した。
B インド亜大陸は,四方を海や高い山脈,大河に囲まれている。古来,北西部のカイバル峠は,人々がインド世界と他の地域との間を往来する際の,数少ない陸の要衝であった。(4)インダス文明の衰退後,(5)この峠を通って様々な文化がインドにもたらされ,またインドの文化も他地域へ伝えられた。16世紀以降になると,海上交通の発展によって,以前にはない規模で多数の人々が海路で移動するようになった。イギリス統治時代,多くのインド人労働者や商人は,船で他の(6)イギリスの植民地に渡ったのであり,今日,世界各地に住むインド系の人々の多くも,このような移民の子孫なのである。
問4 下線部(4)に関連して,古代に使用された次の文字の名アとイと,その文字が刻まれた下の遺物の写真a~cとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【31】
ア 甲骨文字
イ インダス文字
(1) ア―a
イ―b
(2) ア―a
イ―c
(3) ア―b
イ―a
(4) ア―b
イ―c
(5) ア―c
イ―a
(6) ア―c
イ―b
問5 下線部(5)に関連して,南アジアの文化や出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】
問6 下線部(6)に関連して,イギリスの植民地となった地域について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】
C 周辺世界との交流が緊密な中央ユーラシアでは,先住者が,(7)外来の移住者の影響の下に,新たな宗教や言語を受容する現象がしばしば見られた。例えば,中央ユーラシアの西部ではゾロアスター教やネストリウス派キリスト教,東部ではマニ教や仏教が広まっていたが,後に西方からのイスラーム化が急速に進行した。また,トルコ(テュルク)系の(8)遊牧民がオアシス都市に定住するようになると,言語面でのトルコ化が東方から徐々に進んだ。そして,イスラーム化したトルコ系の【(9)】は,11世紀に西方へ進出し,ビザンツ帝国を脅かすようになった。
問7 下線部(7)に関連して,人々の移動や移住について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】
(1) イギリスの
ピューリタンが,北アメリカに移住して植民地を建設した。
(2) ロロの率いるノルマン人の一派が,イギリスにノルマン朝を建てた。
(3) ウマイヤ朝の一族が,小アジアに
後ウマイヤ朝を建てた。
(4) ドイツ騎士団が,レコンキスタ(国土回復運動)を行った。
問8 下線部(8)に関連して,遊牧世界と農耕世界のかかわりについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】
(1) 戦国時代に,
五胡と呼ばれる諸民族が,華北で国を建てた。
(2) エフタルは,突厥と
ササン朝によって滅ぼされた。
(3) 月氏は,
安史の乱の際,唐に援軍を送った。
(4) 匈奴を挟撃するため,後漢の
張騫が西域に派遣された。
問9 文章中の空欄【(9)】に入れる王朝の名と,その王朝の西進の経路を示した次の地図中の矢印aとbとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】