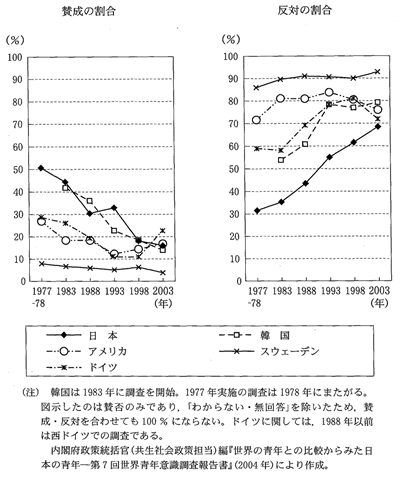2009年度 センター試験【現代社会】問題
(解答番号【1】~【36】)
第1問 高校生(A)とその母親(B)による次の会話文を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)
A:いよいよ(a)裁判員制度が始まるね。お母さんも裁判に参加できるかもしれないんだよ。すごいことだよね。
B:気楽に言わないでよ。そもそもなぜ裁判員制度が導入されたか,知ってる?
A:これまでの裁判が分かりにくくて,国民にとって身近なものじゃなかったから,それを改めるためだよね。国民の司法参加だよ。
B:確かに,最近では社会をより良くするための市民参加の必要性が説かれているし,裁判員制度もその一つと言えるのかな。でも,私たちが(b)裁判にかかわる機会は裁判員制度以外にもあるよね。(c)日本の司法制度が抱える問題も裁判の分かりにくさだけではないし,裁判員制度でそれがすべて解決するわけじゃないでしょ。例えば冤罪の問題はどう?
A:うーん。それもそうだけど,プロの裁判官だって間違った判断を絶対にしないとも限らないよ。市民感覚を取り入れることで,より妥当な結論に近づくこともあると思う。
B:そう考えるとますます裁判員になるのは気が重いな。裁判は,時には判決によって人の生命を奪うことも認めるものだし,思い込みや世論に流されてしまうと逆に(d)人権の重大な侵害を引き起こしかねないでしょう。
A:一人一人の人権感覚が問われることにもなるね。(e)
司法を民主化することも,「人権の砦(
」としての役割をちゃんと果たせるようにすることも,どちらも重要で,確かに難しい問題だなあ。じっくり考えてみるよ。
問1 下線部(a)の概要を記述した次の文章中の【ア】~【ウ】に入る語句の組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(8)のうちから一つ選べ。【1】
日本の
判員制度とは,国政選挙の有権者から【ア】選ばれた裁判員が【イ】について,裁判官と共に事実を認定し,評決をする制度である。裁判員に選ばれた者は正当な理由がない限り辞退することはできないが,学生などには一般に辞退が認められている。裁判員には審理への出頭義務や【ウ】が課せられ,これらの義務違反に対しては罰則も設けられている。
(1) ア 選挙によって イ すべての刑事事件 ウ 氏名の公表義務
(2) ア 選挙によって イ すべての刑事事件 ウ 守秘義務
(3) ア 選挙によって イ 特定の刑事事件 ウ 氏名の公表義務
(4) ア 選挙によって イ 特定の刑事事件 ウ 守秘義務
(5) ア 無作為に イ すべての刑事事件 ウ 氏名の公表義務
(6) ア 無作為に イ すべての刑事事件 ウ 守秘義務
(7) ア 無作為に イ 特定の刑事事件 ウ 氏名の公表義務
(8) ア 無作為に イ 特定の刑事事件 ウ 守秘義務
問2 下線部(b)に関して,日本の状況の説明として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】
(1)
検察審査会は,抽選によって選ばれた国民によって構成され,検察官の不起訴処分の是非について審査する。
(2) 裁判の
傍聴は国民の権利であるが,プライバシーの権利を保障するため,刑事事件については,法定でメモを取ることは許されていない。
(3) 最高裁判所の裁判官に対する
国民審査が憲法上認められているが,この制度により罷免された裁判官はいない。
(4) 犯罪被害者の権利・利益を保護するため,刑事事件において被害者が直接被告人に質問をすることを認める制度が導入されている。
問3 下線部(c)やそれへの対策に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】
(1) 裁判官の独立を保障するため,最高裁判所が下級裁判所の
裁判官の任命に関与することは法的に禁止されている。
(2) 国民の司法へのアクセスを促進するために,法曹人口を増やすなどの
司法制度改革が進められている。
(3) 冤罪に問われた人を救済するため,無罪とすべき明らかな証拠が新たに発見された場合などに,
再審を請求することを認める制度が設けられている。
(4) 裁判に時間がかかり過ぎるとの指摘がなされており,裁判の迅速化を進めるための法律を制定するなどの改革が行われている。
問4 下線部(d)に関して,日本の状況の説明として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】
(1) 憲法には生存権が明記されており,最高裁判所は,これを直接の根拠として,国民は国に
社会保障給付を請求することができるとした。
(2) 名誉を
毀損する行為の禁止が,
表現の自由に対する制約として認められるように,人権であっても,他者を害する場合等には制約されることがある。
(3) 最高裁判所は,裁判所による雑誌の発売前の差止めが,憲法で明示的に禁止されている検閲に該当すると判断した。
(4)
在外投票は外国に居住している国民の選挙権を保証するための手段であるが,日本の国政選挙で実施されたことはなく,制度導入が求められている。
問5 下線部(e)に関連して,民主主義と司法権に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】
(1) 日本国憲法は違憲審査の制度を設けており,最高裁判所だけでなくすべての下級裁判所が
違憲審査権を行使することができる。
(2) 日本国憲法は国民主権を採っているため,国会の制定する法律に基づく政治が行われていれば,「法の支配」に一切反しないとされる。
(3) 大日本帝国憲法は天皇主権をすべてに優越する基本原理としていたが,同時に,裁判所が法律に対して違憲審査権を行使することも認めていた。
(4) 大日本帝国憲法は「臣民の権利」を保障しており,帝国議会が法律によってこれを制限することは一切できないとされていた。
第2問 次の文章を読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 22)
日本の地域社会は,第二次世界大戦後,現在に至るまで大きく変化している。戦後の復興期依頼,(a)農村部から都市部へ急激に人口が移動した。そして1970年代以降,地方都市から大都市への人口移動も進んでいる。また,地方都市では,郊外における宅地開発や,(b)大型商業施設の建設などにより,住民の生活圏の中心が,郊外へ移った。これらの結果,駅前地区など中心市街地の衰退が,1980年代から地方都市へ顕在化するようになった。
中心市街地衰退の影響は,そこに仕事を持つ商工業者だけが受けるわけではない。例えば,郊外へ移住したり車で自ら移動したりすることが困難な高齢者なども,その影響を受けることになる。(c)社会の高齢化が急速に進行しているなかで,中心市街地の再活性化は地域社会にとって重要な課題である。
このような問題の解決には,国が画一的な政策を策定し対処するよりも,(d)地方自治体が地域の実情を踏まえ対処していくことが望ましい。しかし日本ではこれまで,事務執行の方法から財政運営に至るまで様々な制約があり,地域の抱える問題に対して自治体のできる取組みには限界があることが指摘されてきた。そのため,従来の国と地方の関係を見直した(e)地方分権一括法が制定され,自治体が独自の判断と裁量で政策を展開しやすい環境が整備された。自治体の憲法と言われる(f)自治基本条例を制定する自治体もある。また,財政面においても,地方分権改革の一環として(g)「三位一体の改革」が行われた。
しかし自治体の政策だけでは,中心市街地の再活性化は難しい。魅力がなければ住民は中心市街地に足を運ぼうとせず,結局問題は解決しない。そしてその魅力は,外から与えられてかたちづくられるものではない。住民自身も,(h)まちづくりの活動に積極的に参画していくことが求められている。
問1 下線部(a)にかかわって日本の地域社会に起こった現象に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】
(1) 高度経済成長期から,都市部で大気汚染や騒音などの都市・生活型公害が社会問題化し,その対策を求める住民運動が盛んに行われた。
(2) 都市部への人口移動により都市部での児童・生徒数が増えたため,高度経済成長期にそれに対応するための教育特区が設けられた。
(3) 農業振興のための補助金制度が存在しなかったため,都市部への人口移動が起こり,高度経済成長期全体を通して農家数が減少した。
(4) 農家数は減少したが,農家全体に占める専業農家の比率は第二次世界大戦後の農地改革直後よりも増大した。
問2 下線部(b)に関連して,近年の日本での小売業に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】
(1) POS(販売時点情報管理)システムが発達したことにより,商品管理がしやすくなった。
(2) 書籍販売などの分野で,実際の店舗を持たずにインターネットを利用して事業を行う小売業者が出現した。
(3) スーパーマーケットとコンビニエンスストアとは,顧客層が競合するため,系列関係は存在しない。
(4) 老舗百貨店どうしの合併が行われるなど,小売業者の多くが業界再編の圧力を免れていない。
問3 下線部(c)に対応する日本政府による政策に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】
(1) 高齢者が負担する医療費の高さが問題として指摘され,現在,高齢者の医療保険料は原則として無料となっている。
(2) 国民年金の老齢年金については,現在,支給開始年齢が65歳から60歳に引き下げられている。
(3) 在宅介護の充実を目的として,ホームヘルパーの増加などを盛り込んだ政策が実施された。
(4) 介護サービス利用を保障する介護保険制度が導入され,原則として,20歳以上の国民は保険料を納付することが義務づけられた。
問4 下線部(d)に関して,日本の地方自治体の政治機構についての記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】
(1) 首長の補助機関である副知事や副市町村長の就任については,議会の同意を必要としない。
(2) 都道府県や市町村には,執行機関として教育委員会などの行政委員会が置かれている。
(3) 選挙管理委員会の委員は,地方議会の議員経験者などのなかから,住民によって直接選ばれる。
(4) 地方議会は首長に対する不信任決議権を持つが,首長は議会を解散することはできない。
問5 下線部(e)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】
(1) 機関委任事務が新設され,地方で処理した方が効率的な事務は地方自治体に委任された。
(2) 法定受託事務のなかに新たに自治事務が加えられ,地方自治体の事務が再編されている。
(3) 国と地方の関係は対等・協力関係となったので,法廷受託事務についても国の関与はなくなった。
(4) 自治事務においては,法令に違反しない限り,地方自治体が自らの責任と判断で地域の特性に応じた工夫ができる。
問6 下線部(f)に関連して,日本の条例の制定に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】
(1)
地方自治体の首長は,議会に対して条例の審議・制定を要請することはできるが,条例案を提出することはできない。
(2) 地方自治体の首長は,条例の制定に関する議会の議決に対して異議のあるときは,再議に付すことができる。
(3) 条例の制定・改廃について,住民が首長に対して
直接請求する場合には,原則として有権者の3分の1の署名が必要である。
(4) 条例は「法律の範囲内」で制定が可能であり,国の
情報公開法に先んじて情報公開条例を制定した地方自治体はなかった。
問7 下線部(g)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】
(1) 地方自治体の自主性を高めるため,国から地方へ交付される
地方交付税の総額が増やされた。
(2) 地方分権推進委員会がいわゆる
「骨太の方針」に取りまとめ,内閣総理大臣に答申した後,閣議決定された。
(3) 所得税の一部を個人住民税に移譲するというかたちで,国から地方へ税源移譲がなされた。
(4) 地方財政は国への依存度が高いとの批判があったため,国による使途の指定のない
国庫支出金が削減された。
問8 下線部(h)に関連して,高校生が,中心市街地におけるまちづくり活動について,グループで調査研究を行う際の作業に関して,作業の目的A~Cと,作業ア~エとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【13】
A まちづくり活動の実施状況について全般的な傾向を把握するため,多くの調査対象者から情報を集める。
B まちづくりへのニーズについて,調査対象者と対面して,詳細を確認しながら情報を集める。
C 調査地域に必要とされるまちづくりの活動について,調査結果を考察する。
ア 調査研究グループのメンバーのみで
ディスカッションを行う。
イ 調査地域の商工業者に,郵送式の
アンケートを実施する。
ウ 実際に調査地域に行き,中心市街地の利用者にインタビューをする。
エ 地方議会の議員に,調査研究の成果をまとめた
報告書を郵送する。
(1) A-ア B-エ C-イ
(2) A-ア B-エ C-ウ
(3) A-イ B-ウ C-ア
(4) A-イ B-ア C-ウ
(5) A-エ B-ウ C-ア
(6) A-エ B-ア C-イ
第3問 次の文章を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)
社会変化の原動力の一つは技術革新(イノベーション)である。近年の情報技術革新は,人々のコミュニケーションの仕方から商慣習の在り方まで広範な影響を与えてきた。インターネットが生活を便利にする一方で,(a)知的所有権(知的財産権)をめぐる紛争や,情報格差(デジタルデバイド)の問題が深刻化している。このように,(b)技術革新は経済や社会の在り方を変容させてきた。
技術革新の主要な担い手は民間企業である。技術革新を通じて,古いものを打ち壊し,新しいものを創造することで,(c)経済の発展に貢献してきた企業も多い。多額の資金を必要とする研究開発には,大企業が有利である。しかし,中小企業のなかでも,独自の技術やアイデアを核に新たに事業を興した企業が活躍している。
こうした企業は(d)ベンチャービジネスと呼ばれている。ベンチャービジネスを立ち上げるのは起業家である。起業家のなかには,利益をあげつつ社会貢献を果たそうとする社会起業家と呼ばれる人々も存在する。そのよく知られた例は,ノーベル平和賞を受賞したムハマド・ユヌスである。彼は,グラミン銀行を設立し,既存の銀行では不可能だと思われていた貧しい女性らの零細な事業に対する融資(マクロクレジット)を行って,多くの人々を貧困から解放した。
技術革新を社会発展に結び付けるために,起業家が果たし得る役割は大きい。技術革新がどのようにいかされていくかは,事業化に挑む起業家のビジョンや使命感に左右されるからだ。それだけに起業家には,個人的な利潤の追求だけでなく,事業を通じての(e)▽社会への貢献が求められている。
問1 下線部(a)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】
(1) 知的所有権が関税と貿易に関する一般協定(GATT)のケネディ・ラウンドにおける交渉分野の一つとして取り上げられた。
(2) 知的所有権の範囲は,世界知的所有権機関(WIPO)によって国際的に統一されており,各国間の相違はない。
(3) 知的所有権をめぐる紛争は,中国やインドなど新興工業国と,先進工業国との間では生じていない。
(4) 知的所有権は,それが保護している対象がコンピュータソフトのように複製や模倣が容易なものが多く,権利侵害に対して脆弱な面を持つ。
問2 下線部(b)に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】
(1) イギリスの産業革命では,蒸気機関の導入などによって生産力が増大したが,子どもの長時間労働等が深刻な社会問題となった。
(2) デジタル技術の発達を基盤としたIT革命によって,日本では携帯電話などの情報端末を利用した音楽配信等の多様なサービスが普及した。
(3) ベルトコンベアの発明などによって傾斜生産方式が確立したことで,自動車が大衆の乗り物や輸送手段として普及した。
(4) バイオテクノロジーを用いて作り出された農作物などが,生態系に悪影響を及ぼしかねないと指摘されている。
問3 下線部(c)に関する次の記述A~Dと,それらと関係の深い人名ア~オとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【16】
A 外国貿易において,各国は比較的優位にある商品の生産に特化し,それを輸出し合えば,双方が利益を得られる。
B 企業が古いものを破壊し新しいものを生み出す創造的破壊や技術革新を繰り返すことによって,経済は発展する。
C 経済が発展するにつれ,産業構造は,第一次産業から第二次産業へ,そして第三次産業へと重心を移していく傾向を持つ。
D 各人による利己的な利益の追求が,結果として,社会全体の利益につながる。
ア アダム・スミス
イ アマルティア・セン
ウ ウィリアム・ペティとコリン・クラーク
エ ジョセフ・シュンペーター
オ デビッド・リカード
(1) A-ア B-ウ C-エ D-オ
(2) A-ア B-ウ C-エ D-イ
(3) A-イ B-ウ C-エ D-オ
(4) A-イ B-エ C-ウ D-ア
(5) A-オ B-エ C-ウ D-イ
(6) A-オ B-エ C-ウ D-ア
問4 下線部(d)に関連して,次の文章の【A】~【C】に入る語句の組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(8)のうちから一つ選べ。【17】
ベンチャービジネスが盛んなことで有名な【A】は,ベンチャー投資がアメリカのなかで最も集中している地域である。そこには,大学などでの研究成果を事業化するベンチャービジネスに,資金や専門知識を提供する専門家・専門機関が数多く集まっている。起業家は,自分や家族の蓄えを資金とするのみならず,エンジェルと呼ばれる個人投資家や【B】から資金の提供を受ける場合が多い。独自技術を用いて事業化を図る場合,知的財産の管理が重要なので,前もって【C】などによる専門的なアドバイスを受けやすい環境が起業に役立つ。経済の発展にはこのような起業環境の整備も重要である。
(1) A シリコンバレー B ベンチャーキャピタル C 弁護士
(2) A シリコンバレー B ベンチャーキャピタル C 裁判官
(3) A シリコンバレー B ファイナンシャルプランナー C 弁護士
(4) A シリコンバレー B ファイナンシャルプランナー C 裁判官
(5) A ウォール街 B ベンチャーキャピタル C 弁護士
(6) A ウォール街 B ベンチャーキャピタル C 裁判官
(7) A ウォール街 B ファイナンシャルプランナー C 弁護士
(8) A ウォール街 B ファイナンシャルプランナー C 裁判官
問5 下線部(e)に関連して,社会的責任や社会貢献を重視した企業の取組みや在り方に関する説明として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】
(1) 企業が環境対策に費やした経費や企業活動が環境に及ぼした影響などを認識・測定し,公表する試みが行われている。
(2) 企業が芸術や文化活動の支援を行うことをメセナというが,日本においてこうした活動はまだ行われていない。
(3) 環境保護といった社会的に重要な問題に積極的に取り組む企業を選別し,そうした企業の株式へ選択的に投資することが行われている。
(4) 社会起業家が利用している企業形態は多様であり,株式会社形態のみが利用されているわけではない。
第4問 高校生(A)とその父親(B)による次の会話文を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)
A:この前,車のフロントガラスに積もってたのは黄砂だったんでしょ? すごかったね。どうして最近,こんなに黄砂が増えたんだろうね。地球環境の問題かなぁ。
B:学校では(a)
環境問題についてどう習ってるの?
A:小学生のときは野外で(b)
自然や生き物の大切さを学んだり,高校では
地球環境問題と
公害問題について広く学んだりしてるよ。
B:いいことを学んでるね。
A:確かに環境がどうなっているかについては学べているけど,環境問題の解決には何をしたら良いかってことにむしろ私の関心があるの。(c)
行動しても他の問題を引き起こすことがあったりするから,行動の前にはある程度考えた方がいい場合もあるでしょう?
B:難しいことはよく分からないけど,
“Think Globally, Act Locally(地球レベルで考えて,地域レベルで行動しよう)”って言うし,マイバッグを持ったり,冷房を28度に設定したりすればいいんじゃないのかな?
A:うーん。それって身近にできる対策ではあるけど,地域レベルの行動としてマイバッグを持つことが,地球レベルで見て黄砂の問題につながるのかなぁ。
B:あんまりつながらないってこと? でもよく話題になる(d)
地球温暖化問題とか(e)
廃棄物問題とかにはつながるだろう?
A:それはそうね。でも,黄砂は,温暖化や廃棄物との関連性は低いと思うの。私は黄砂についてもっと調べてみることにする。
B:お父さんは温暖化についてもっと勉強してみるから,そのうちまた議論してみるか。
問1 下線部(a)は「
外部不経済」の観点から
捉えることができる。外部不経済に該当する例として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】
(1) 日本の小説や漫画が外国で合法的に翻訳・流通・販売され,その外国で出版されてきた小説や漫画の売り上げが下がること。
(2) 企業が自社の環境問題への取組みの様子を広報するために多くの費用をかけること。
(3) 企業による屋外の音楽イベントを,地域住民が騒音と感じること。
(4) 商業用ビルのクリスマスのイルミネーションを人々が見て楽しむこと。
問2 下線部(b)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】
(1) ワシントン条約は,世界の生物多様性の保全などを目的として,リオデジャネイロで開催された地球サミットにおいて採択された条約である。
(2) 捕鯨については,生態系のバランス,鯨という動物の文化的位置づけなど様々な観点から,意見の対立が続いている。
(3) ラムサール条約は,世界遺産のうちの自然遺産の保護を目的とする条約で,日本国内では既に数か所が登録されている。
(4) ナショナルトラスト運動における希少野生動物を買い取って保護するという方法については意見の対立が続いている。
問3 下線部(c)に相当する例として「自家用車で
リサイクルステーションまで古紙を運ぶ活動」が挙げられる。この活動が盛んになった場合の,「森林資源使用量」と「古紙運搬時のエネルギー使用量」の増減の様子として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】
(1) 「森林資源使用量」が増え,「古紙運搬時のエネルギー使用量」が増える。
(2) 「森林資源使用量」が増え,「古紙運搬時のエネルギー使用量」が減る。
(3) 「森林資源使用量」が減り,「古紙運搬時のエネルギー使用量」が増える。
(4) 「森林資源使用量」が減り,「古紙運搬時のエネルギー使用量」が減る。
問4 下線部(d)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】
(1) 京都議定書が発効まで時間を要したのは,二酸化炭素(CO2)排出量の多い国の一部が批准せず,発効のための要件が満たされなかったためである。
(2) 京都議定書を採択した会議(COP3)では日本が議長国だったので,温室効果ガス削減割合目標は締約国のなかで一番高い6%という値が設定された。
(3) 原子力発電はCO2排出量が少ないにもかかわらず,日本政府がCO2排出量削減手段として位置づけていないのは,放射能汚染を危惧するためである。
(4) 水蒸気は温室効果ガスであり,削減すべき温室効果ガスとして日本政府が位置づけている。
問5 下線部(e)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】
(1) 廃棄物問題の解決に向け,日本が目指すのは大量生産・大量消費・大量リサイクルを特徴とする「大量リサイクル社会」であると法律に明記されている。
(2) 家電リサイクル法が回収と再資源化を義務づけているのはテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンである。
(3) 廃棄物問題の解決に向け,各家庭で行われるべきごみ・資源全般の分け方や出し方が全国一律に定められた。
(4) 友人からもらった古着を着用することは,3R(リデュース・リユース・リサイクル)のなかのリサイクルの例に該当する。
第5問 次の文章を読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 22)
世界各地がますます密接につながる動きを,地球全体を意味する【グローバル】という言葉を使って「グローバル化」と言う。この動きの中心に(a)市場経済の世界的な一体化があり,これを指して(b)経済のグローバル化と呼ぶ。冷戦後の時代の変化や特徴をよく捉えた用語である。電子メールや携帯電話の普及により,世界は一つにつながりつつあるという実感は深まった。しかし,グローバル化には負の側面もあり,「地球全体」という語義と地球の現実との間には距離もある。
第一に,グローバル化の恩恵は必ずしも「地球全体」に行き渡ってはいない。(c)インターネットへの常時接続が当たり前の「世界」と,電信・電話はおろか,水道・電気・ガスといったライフライン(命綱)の確保すら困難な「世界」が,地球上に併存している。第二に,地球環境問題がある。温暖化にも酸性雨にも国境はない。人類の地球規模での活動が,地球の自浄作用の限界に突き当たったとも言えよう。第三に,(d)人々の交流が緊密になればなるほど,「地球市民」としての一体感が高まる一方で,(e)民族,文化,宗教の違いによる摩擦や対立も生まれがちになる。世界を一つに結び付ける(f)統合作用と地球規模での分断作用の二つが同時進行中なのである。
グローバル化の恩恵にあずかりその波に乗れる人たちにとっては「国境なき世界」が実現しつつあるが,グローバル化に取り残された人々にとっては,国境の壁はむしろ高くなってしまった。国境を越えられず国内で避難する人々や隣国の難民キャンプでの生活を余儀なくされる人々のように,「国」を失って最低限の(g)人権や(h)安全すら保障されない状態に追い込まれた人たちもいる。グローバル化という言葉とその言葉が指し示すはずの現実との距離に,私たちは常に目を向けなくてはならない。
問1 下線部(a)の促進要因についての記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】
問2 下線部(b)に関連して,1990年代にアジアなどで起こった
通貨危機に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】
(1) 貿易赤字の拡大を問題視した,アメリカの連邦議会主導による反ダンピング政策が,通貨危機の原因である。
(2) 1990年代初めに起こった日本でのバブル経済の崩壊が,近隣アジア諸国における通貨危機を直接引き起こしたとされている。
(3) 通貨危機後,国際労働機関(ILO)による融資が行われたが,その際各国に対して厳しい経済構造調整が求められた。
(4) 通貨危機の原因として,短期的な資金運用を行う金融機関や投資家の行動が指摘されている。
問3 下線部(c)に関連して,国際社会における経済格差や,その是正のための取組みについての記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】
問4 下線部(d)に関連して,次の二つの表は,日本で学ぶ外国人留学生や海外で学ぶ日本人留学生の人数を示したもの(表1)と,外国人留学生の出身国・地域を多い順に並べたもの(表2)である。これらの表から読み取れることとして適当でないものを,次ページの(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

出身別外国人留学生数及び留学先別日本人留学生数

出身国・地域別に見た外国人留学生数〔上位5番目まで〕
(注)表1・表2において,留学生とは日本人・外国人とも大学等高等教育機関の在籍者のみ(なお,外国人留学生数は,各年5月1日現在の人数)。
文部科学省高等教育局『我が国の留学生制度の概要―受入れ及び派遣―』(平成13,15,17,19年度)により作成。
(1) いずれの調査対象年も,北米からの留学生の数はアジアからの留学生の数より少ないが,北米を留学先とする日本人留学生の数はアジアを留学先とする日本人留学生の数より多い。
(2) 2000年と比較して2002年・2004年とも,欧州を留学先とする日本人留学生の数も北米を留学先とする日本人留学生の数も増加している。
(3) 日本で学ぶ外国人留学生全体に占めるアジアからの留学生の割合は,いずれの調査対象年も9割を超えている。
(4) 2000年から2004年にかけての外国人留学生の増加数に占める割合はアジアからの留学生の増加数が最大で,アジアからの留学生のなかでも中国からの留学生の増加数が最も多い。
問5 下線部(e)に関連して,異文化理解にかかわりの深い次の用語A~Cと,その説明ア~エとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【28】
A マルチカルチュラリズム
B ステレオタイプ
C エスノセントリズム
ア 単純な二分法や固定的なパターンにより,事実を認識したり理解したりする
捉え方及び捉えられたイメージ。
イ 様々な文化にはそれぞれ違いは見られるが優劣はないとし,文化的な多様性を尊重する主張。
ウ 自民族の文化の優越性を主張し,自らの基準をもって異文化を過小に評価する考え方。
エ 合理的な理由や正しい認識を持たない,感情的で否定的かつ差別的な態度や見方。
(1) A-ア B-イ C-ウ
(2) A-ア B-ウ C-エ
(3) A-イ B-エ C-ア
(4) A-イ B-ア C-ウ
(5) A-ウ B-エ C-イ
(6) A-ウ B-ア C-エ
問6 下線部(f)に関連して,冷戦後の地域統合や地域機構についての記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】
問7 下線部(g)に関して,日本における外国人の人権状況の記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】
(1) 最高裁判所は,憲法の保障する権利は国民固有の権利であり,外国人の人権は政策的に認められているにすぎないとしている。。
(2) 最高裁判所は,日本に永住している外国人に対して国政選挙における選挙権を付与することは,憲法上禁止されていないとの判断を示した。
(3) 外国人が単純労働者の資格で入国することは可能となったが,その労働条件や生活支援などの面で問題が指摘されている。
(4) 外国人に対しても請願権は保障されており,国会などに請願を行うことができる。
問8 下線部(h)に関連して,安全保障の在り方や考え方に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】
(1) 国際連合(国連)は,新たな感染症の世界的流行も国際社会の安全への重大な脅威とみなし,危機的状況に際しての対応を国連軍の任務に加えている。
(2) 国連安全保障理事会による非軍事的措置は,国連憲章に基づき,国連事務総長の指揮の下に行われる。
(3) 国連は,国家ではなく個々の人間に着目する「人間の安全保障」に基づく活動を展開している。
(4) 日本国憲法は,日本が集団的自衛権の行使をする際には,国連安全保障理事会の承認を必要とすると規定している。
第6問 次の文章を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)
人の一生のなかで,(a)
青年期は心身両面にわたる「
第二の誕生」の時期である。「青年期」を発見したと言われるルソーは,「我々はいわば二度生まれる。一度目は生存するために,二度目は生きるために。一度目は人類の一員として,二度目は性を持った人間として。」という言葉で端的にそれを表現した。この時期に青年の多くは,自覚的・主体的に自己をつくる課題と直面する。また,
第二次性徴の発現に伴う身体的成熟や(b)
ジェンダーの問題と向き合い,さらには,これまで疑問を持つことなく受け入れてきた既存の価値にも懐疑的になりがちである。このような新たな状況下で(c)
自分の欲求をうまく満たせず,不適応感を覚えることもあるだろう。
青年期は,誕生以来身近であった親との関係や友人関係に,変化が起きる時期だとも言われる。(d)
児童期の安定した親子関係は揺らぎ,その関係性が再構築される過程で,親と子はそれぞれ
葛藤を抱えることが多くなる。
親に代わって青年の心を受け止め,支える存在としての友人との関係は,さらに重要度を増すだろう。時には反目や対立で心が深く傷つくこともある。しかし,友人とのかかわりは,親とのかかわりとは異なる側面で,青年の(e)
自己形成に計り知れない影響をもたらすことが多い。
自己の内外に生じる多様な変化のなかで,自己と向き合い,「自分らしさ」を探求すること,それは,一人の大人としてより良く「自分を生きる」段階へ向かうために,避けることのできない重要な課題である。
問1 下線部(a)に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】
(1) マズローは,青年を,大人と子どもの集団の境界に位置しながらも,いずれの集団にも属さない周辺人(境界人)と呼んだ。
(2) ハヴィガーストは,親や他の大人からの情緒的自立など,大人になる過程で青年が取り組むべき発達課題を提唱した。
(3) 親や教師などからの保護を束縛や強制と感じ,親や教師などに否定的態度を示す青年期の一時期は,第二反抗期と呼ばれている。
(4) 青年期の始まりを告げる急激な身体的変化は,心理的な成熟に先立って現れるとされている。
問2 下線部(b)に関連して,次の図は5か国の青年(18~24歳)に,「男は外で働き,女は家庭を守るべきだ」という男女の役割観についての賛否を尋ねた調査結果を示したものである。図から読み取れることとして最も適当なものを,次ページの(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】
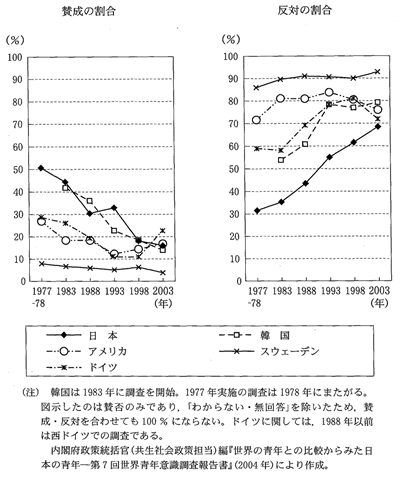
(1) 日本は,いずれの年の調査においても,5か国のうちで「賛成」の割合が最も高い。
(2) スウェーデンやアメリカは,「反対」の割合が他の国よりも高く,各年の調査を通じて,一貫して80%を超えている。
(3) 日本では,1988年以降,調査対象の各年を通じて,「反対」の割合が「賛成」の割合より高くなっている。
(4) 韓国・ドイツでは,調査を重ねるごとに「賛成」の割合が一貫して低下している。
問3 下線部(c)に関して,自我の
防衛機制(防衛反応)により一時的・消極的な問題解決が図られることがあるが,これに関する次の用語A~Cとその説明
ア~エとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(8)のうちから一つ選べ。【34】
A 同一視
B 反動形成
C 抑圧
ア 大切な人との死別など受け入れ難い現実を避けて,空想の世界に埋没すること。
イ 憧れや尊敬の対象となる人物のファッション,髪型,言動などを取り入れて,似たように振る舞うこと。
ウ 自分にとって苦痛や不安を起こさせる出来事について,思い出さない仕組みが働くこと。
エ 好きな人に対してその人の嫌がることをするなど,自分の欲求とは逆の発言や行為をすること。
(1) A-ア B-イ C-エ
(2) A-イ B-エ C-ウ
(3) A-ウ B-ア C-エ
(4) A-エ B-ア C-ウ
(5) A-ア B-エ C-イ
(6) A-イ B-ウ C-ア
(7) A-ウ B-イ C-ア
(8) A-エ B-ウ C-イ
問4 下線部(d)に関連して,親や友人をはじめとする周囲の人々と青年との関係についての記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】
(1) 青年期には,他者のまなざしを強く意識し,周囲の人々との関係に注意が向くため,自己の内面を見つめることがないとされる。
(2) 青年期では,共通する興味や関心を持ち,互いに認め支え合う友人関係を求めるとされる。
(3) 青年期には,親に反発しつつ甘え,理解を求めつつも離反するなどといった相反する態度をとるとされる。
(4) 青年期に劣等感が強く意識されるのは,目に見えて急激に変化する身体をはじめ,自己と他者の違いに向き合うことが多くなるからとされる。
問5 下線部(e)に関連して,次の文章の【A】~【C】に入る語句の組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(8)のうちから一つ選べ。【36】
アメリカの心理学者・精神分析学者であるエリクソンは,青年期の心理・社会的課題が達成されていない状態として,【A】を挙げている。【A】は,自分は自分であるという主観的な感覚及びその【B】が持てない状態であり,そのため【C】に陥り何事にも意欲がわかないこともある。
(1) A-アイデンティティ拡散 B-連帯性 C-自己愛
(2) A-アイデンティティ拡散 B-連帯性 C-アパシー
(3) A-アイデンティティ拡散 B-連続性 C-自己愛
(4) A-アイデンティティ拡散 B-連続性 C-アパシー
(5) A-コンフリクト B-連帯性 C-自己愛
(6) A-コンフリクト B-連帯性 C-アパシー
(7) A-コンフリクト B-連続性 C-自己愛
(8) A-コンフリクト B-連続性 C-アパシー