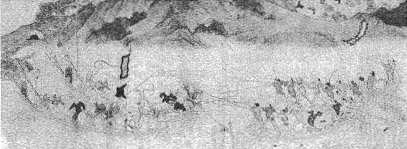2004年度 センター試験【日本史B】問題
(解答番号【1】~【36】)
第1問 古代から現代までの学校と学問に関するA~Cの文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 17)
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】
(1) ア 大学別曹
イ 最澄
(2) ア  イ
イ 最澄
(3) ア 大学別曹
イ 空海
(4) ア  イ
イ 空海
問2 下線部(a)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】
(1) 桂庵玄樹は,肥後の菊池氏に招かれ海南学派を興した。
(2) 桂庵玄樹は,薩摩の島津氏に招かれ薩南学派を興した。
(3) 絶海中津は,肥後の菊池氏に招かれ海南学派を興した。
(4) 絶海中津は,薩摩の島津氏に招かれ薩南学派を興した。
問3 下線部(b)に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】
(1) この学問所は,のちに昌平坂学問所となった。
(2) この学問所では,『古事記伝』が編纂された。
(3) 徳川綱吉は,朱子学以外の学派を異学と定めた。
(4) 徳川綱吉は,林鵞峰を大学頭に任命した。
問4 下線部(c)について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】
(1) 心学は,商人の商業活動を正当なものとして認めた。
(2) 心学は,儒教道徳に仏教・神道の教えを取り入れてつくられた。
(3) 心学は,山片蟠桃らによって全国に広められた。
(4) 心学は,倹約・正直などの徳目を庶民に説いた。
C 明治政府は1871年文部省を設置し,フランスなどに範をとりながら,翌年には学制を発布した。それは,「学問は身を
立(るの
財本(」であるとする実学主義に立ち,「
邑(に不学の戸なく家に不学の人なからしめん」との国民皆学の理念の下に,
(d)近代的な学校教育制度の確立をめざしたものであった。しかし,現実には,当時の国家財政や国民の実情に適合しなかった。そのため,その後の試行錯誤を経て,1886年に学校令ならびに諸学校通則が制定され,ここに学校教育体系の基本的枠組みが成立した。(e)
その枠組みは,若干の改変を経ながらも,第二次世界大戦後に新学制が制定されるまで続いた。
問5 下線部(d)に関連して,19世紀後半の教育・思想について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】
(1) 中江兆民は,『民約訳解』でヘボンの思想を紹介した。
(2) 福沢諭吉は,慶応義塾を創立した。
(3) 人間の自由・平等を説いた天賦人権思想が導入された。
(4) 新島襄は,同志社(同志社英学校)を創立した。
問6 下線部(e)に関連して,この間に起こった出来事を述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】
I 大学令が公布され,公立・私立大学の設立が認められた。
II 宇垣一成陸相の下で,中等学校以上に軍事教練が導入された。
III 義務教育の年限が4年から6年に延長された。
(1) I-II-III
(2) II-I-III
(3) III-I-II
(4) III-II-I
第2問 古代の行政機構や政務運営に関するA・Bの文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 17)
問1 下線部(a)に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】
(1) 豪族の氏の名称は,葛城氏のように朝廷における職掌に由来していた。
(2) 古墳時代には,豪族の権威を象徴するものとして,銅鐸が作られた。
(3) 6世紀に入ると,豪族を葬る古墳の施設として,横穴式石室が普及した。
(4) 壬申の乱で,それまで大きな勢力を持っていた物部氏が没落した。
問2 下線部(b)に関連して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】
(1) 官人の給与のなかには,その位階・官職に応じて支給される禄があった。
(2) 大臣などの上級官人には,職田が支給された。
(3) 位田は,軍事的功績に応じて支給された。
(4) 給与だけでなく,税負担の免除も官人の特権であった。
問3 下線部(c)に関連して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】
(1) 中央の役所で雑務を行った仕丁は,公民から徴発された。
(2) 和同開珎が発行され,政府の流通促進策により,銭貨は全国各地で流通するようになった。
(3) 碁盤の目状に土地を区画する条里制によって,都城や農村の土地を把握した。
(4) 大宝律令の制定により,官有の賤民(は五色の賤に区分された。
問4 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】
(1) ア 経国集 イ 更級日記
(2) ア 令義解 イ 更級日記
(3) ア 経国集 イ 小右記
(4) ア 令義解 イ 小右記
問5 下線部(d)に関連して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】
I 坂上田村麻呂が征夷大将軍に任じられた。
II 仏教を重んじた称徳天皇は,太政大臣禅師の地位を設けた。
III 薬子の変に先立ち,勅命の伝達にかかわる蔵人頭が任じられた。
(1) I-II-III
(2) II-I-III
(3) II-III-I
(4) III-II-I
問6 下線部(e)に関連して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】
(1) 紫香楽で造立が開始された盧舎那仏は,平城京に都が戻されたのちに東大寺の大仏として完成した。
(2) 薬師寺吉祥天像は,奈良時代を代表する仏教彫刻である。
(3) 東大寺に現存する奈良時代の建造物の一つとして,大仏殿(金堂)がある。
(4) 平城京への遷都にともない,大安寺・唐招提寺などの大寺院も建立された。
第3問 中世の政治・社会に関するA・Bの文章・史料を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 17)
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】
(1) ア 宝治合戦 イ 和田義盛
(2) ア 宝治合戦 イ 安達泰盛
(3) ア 霜月騒動 イ 和田義盛
(4) ア 霜月騒動 イ 安達泰盛
問2 下線部(a)の人物が行った政策について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】
(1) 有力御家人や政務にすぐれた人々を選んで,評定衆を創設した。
(2) 後嵯峨天皇の子宗尊親王を鎌倉幕府の将軍に迎えた。
(3) 前将軍九条(藤原)頼経を京都へ送還した。
(4) 裁判の迅速化をはかるため,新たに引付衆を設置した。
問3 下線部(b)に関連して,この時期の出来事を描いた絵として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】


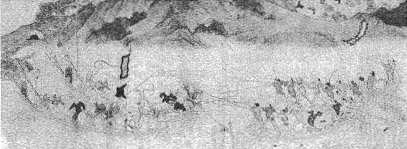

B
(文明十七年十二月)十一日,今日山城国人集会す。上は六十歳,下は十五六歳と
云々(。同じく一国中の土民等群集す。今度両陣の
時宜((注)を申し定めんがための故と云々。しかるべきか。但し,また
【ウ】のいたりなり。両陣の返事・問答の様いかん,いまだ聞かず。
十七日,(c)
両陣の武家衆各引退(き了(んぬ。山城一国中の国人等申し合わす故なり。自今以後においては,両
【エ】方は国中に入るべからず。
(
『大乗院寺社雑事記』)
(注)「時宜」とは,適当な処置のこと。
問4 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】
(1) ウ 一味同心 エ 斯波
(2) ウ 一味同心 エ 畠山
(3) ウ 下克上 エ 畠山
(4) ウ 下克上 イ 斯波
問5 下線部(c)に関して述べた文として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】
(1) 両陣の武家衆は,山城の国人たちとの合戦に敗れて退いた。
(2) 両陣の武家衆は,山城の国人たちに家臣として組織されていた。
(3) このあと,山城の国人たちの協議による自治が8年間続いた。
(4) 山城の国人たちは,本願寺の命令を受けて行動していた。
問6 この史料に関連して,15世紀後半の社会や文化について述べた次の文X~Zについて,その正誤の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】
X キリスト教が伝来し,西日本を中心に広まった。
Y 日親の布教活動により,日蓮宗が京都を中心に西日本各地に広まった。
Z 連歌の規則書である『応安新式』が作られた。
(1) X 正 Y 正 Z 誤
(2) X 正 Y 誤 Z 誤
(3) X 誤 Y 正 Z 正
(4) X 誤 Y 正 Z 誤
第4問 近世の対外関係や蝦夷地に関するA・Bの文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 17)
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】
(1) ア シャム イ 高山右近
(2) ア シャム イ 田中勝介(勝助)
(3) ア カンボジア イ 高山右近
(4) ア カンボジア イ 田中勝介(勝助)
問2 下線部(a)に関連して,日本にやってきた外国人や船について述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】
I イエズス会の宣教師シドッチが,屋久島に潜入した。
II イギリス船フェートン号が,オランダ船を追って長崎に侵入した。
III ウィリアム=アダムズらが乗ったリーフデ号が,豊後臼杵に漂着した。
(1) I-II-III
(2) II-I-III
(3) II-III-I
(4) III-I-II
問3 下線部(b)の時期の建造物甲・乙について述べた文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】


a
甲は,徳川家康を
祀(る
 (
(の門である。
b
甲は,儒学の祖である孔子を祀る

の門である。
c
乙は,
俳諧(の流行を受けて造られた権現造の代表的建造物である。
d
乙は,茶の湯の流行を受けて造られた数寄屋造の代表的建造物である。
(1) a・c
(2) a・d
(3) b・c
(4) b・d
問4 下線部(c)に関して,江戸時代の北方関係について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】
(1) 最上徳内は,シベリア方面を探検した。
(2) ラクスマンは,高田屋嘉兵衛をともなって根室に来航した。
(3) 伊能忠敬は,蝦夷地の沿岸部を測量した。
(4) レザノフは,大黒屋光太夫(幸太夫)をともなって根室に来航した。
問5 下線部(d)に関連して,江戸時代に起こった事件や騒乱について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】
(1) 生野の変は,開国派の武士たちが生野代官所を襲撃した事件である。
(2) 国学者の生田万は,越後柏崎の代官所を襲撃した。
(3) 慶安の変は,由井正雪を首謀者とする幕府転覆の未遂事件である。
(4) シャクシャインは,アイヌの人々を率いて松前藩に反抗した。
問6 下線部(e)に関連して,江戸時代の衣服や染色について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】
(1) 僧侶(の紫衣着用は,寺院法度で定められた。
(2) 麻織物の特産品として奈良晒(や越後縮があった。
(3) 朱色の染料に用いる藍(が,出羽最上地方で作付けされた。
(4) 本阿弥光悦が,友禅染の技法を開発した。
第5問 近現代の技術発展と社会に関するA~Cの文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 21)
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】
(1) ア 官営工場 イ コンドル
(2) ア 官営工場 イ クラーク
(3) ア 株式会社 イ コンドル
(4) ア 株式会社 イ クラーク
問2 下線部(a)に関して,幕末に行われた事柄について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】
(1) 幕府は洋学者渡辺崋山を重用して,国防を強化した。
(2) 幕府は樺太の防衛と開発のため,屯田兵の制度を設けた。
(3) 佐賀藩は反射炉を築造し,大砲を鋳造した。
(4) 薩摩・長州・土佐の各藩は徴兵令を発した。
問3 下線部(b)に関して,1880年代までに行われた事柄を述べた次の文X~Zについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】
X 郵便制度や電信事業がはじまった。
Y 大阪紡績会社はガラ紡を利用して大量生産を実現した。
Z 工部省によって鉄道が整備された。
(1) X 正 Y 正 Z 誤
(2) X 正 Y 誤 Z 正
(3) X 誤 Y 正 Z 誤
(4) X 誤 Y 誤 Z 正
B 第一次世界大戦が起こると,ヨーロッパからの輸入は減少した。従来日本では国産化することが困難であり,輸入に依存していた
【ウ】や化学製品の一部は深刻な品不足となった。この結果,大戦中から戦後の数年の間に,最新技術を導入して国産化する動きが本格的になった。国家や財閥の出資によって設立された
【エ】は,独自に開発した新技術の実用化を次々と進め,のちに新興財閥とよばれた。
(c)自然科学分野の研究成果も生み出され,世界に先駆ける最新技術も開発されるようになった。また大都市を中心に,
(d)技術発展の成果が国民生活に身近なものとなり,近代的な都市空間や生活スタイルが生まれた。
問4 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】
(1) ウ 機械 エ 理化学研究所(理研)
(2) ウ 機械 エ 航空研究所
(3) ウ 綿布 エ 理化学研究所(理研)
(4) ウ 綿布 イ 航空研究所
問5 下線部(c)に関連して,この時代に活躍した本多光太郎の業績として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】
(1) 超短波用アンテナを発明し,電波技術の発展に貢献した。
(2) KS磁石鋼を発明し,鉄鋼技術の発展につとめた。
(3) 原子構造の研究を進め,物理学の発展に寄与した。
(4) 細菌学の研究に成果を残し,伝染病研究所を創設した。
問6 下線部(d)に関して,第一次世界大戦から1930年代までの間に起こった出来事について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】
(1) ラジオ放送がはじまり,日本放送協会が設立された。
(2) 東京・大阪などの大都市では,鉄筋コンクリートのビルディングが建ち並ぶようになった。
(3) 照明器具として,ガス灯が一般家庭に普及した。
(4) 化学肥料の生産増加と普及によって,食糧の増産がはかられた。
問7 下線部(e)について,1950年代から60年代に起こった出来事を述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】
(1) テレビ放送がはじまり,大量の情報が一般家庭に伝えられるようになった。
(2) 原子力の平和利用をうたい,原子力研究所が発足した。
(3) 名神高速道路が開通し,輸送の高速化が進んだ。
(4) 産業用ロボットが普及し,工場生産の自動化が進んだ。
問8 下線部(f)に関連して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】
I 日ソ共同宣言によってソ連との国交が正常化された。
II 最初の先進国首脳会議(サミット)が開かれ,日本もこれに参加した。
III IMF8条国に移行し,いっそうの貿易と資本の自由化を進めた。
(1) I-III-II
(2) II-I-III
(3) III-I-II
(4) III-II-I
第6問 近現代の社会・政治に関するA・Bの文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 11)
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】
(1) ア 成金 イ 河上肇
(2) ア 軍閥 イ 河上肇
(3) ア 成金 イ 賀川豊彦
(4) ア 軍閥 イ 賀川豊彦
問2 下線部(a)に該当する著作として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】
(1) 『日本改造法案大綱』
(2) 『日本資本主義発達史講座』
(3) 『暗夜行路』
(4) 『国防の本義と其強化の提唱』(陸軍パンフレット)
問3 下線部(b)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】
(1) この内閣は,「寛容と忍耐」を唱えた。
(2) この内閣は,沖縄の日本への返還を実現させた。
(3) この内閣のときに,リクルート事件が起こった。
(4) この内閣のときに,第4次中東戦争が起こった。
問4 下線部(c)について,この人物の氏名と,この人物が記者をつとめていた雑誌の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】
(1) 三木武夫-『太陽』
(2) 三木武夫-『東洋経済新報』
(3) 石橋湛山-『太陽』
(4) 石橋湛山-『東洋経済新報』