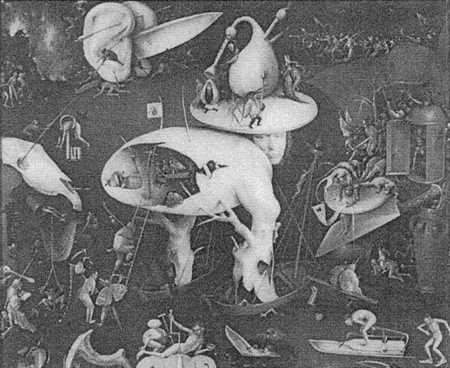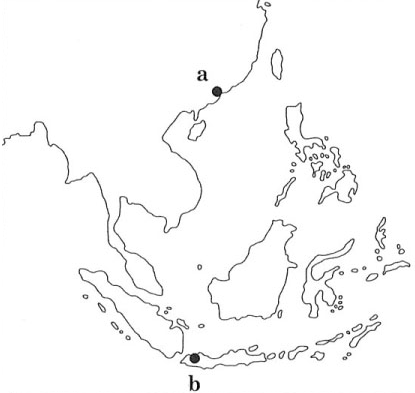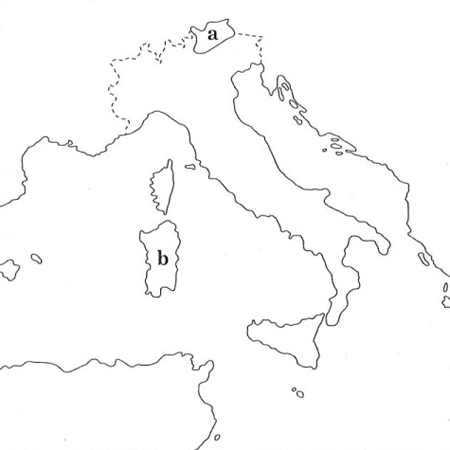2012年度 センター試験【世界史B】問題
(解答番号【1】~【36】)
第1問 人類は,死と向き合うなかで,葬送儀礼から来世への信仰に至るまで様々な文化を発展させてきた。世界史における「死の文化」について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)
A 近年発掘された前漢初期のある墓から,そのころの(1)法律文書が大量に発見された。こうした文書を墓に納めたのは,葬られた人物が生前役人であったからだ,とする指摘がある。当時の人々は,死後も生きていた時と同じ生活を続けるものと信じており,それ故に遺族は故人があの世で困らぬよう生前使用していた遺品を(2)副葬品として納めたと考えられる。また,後漢代では,墓室の壁面などを画像で飾ることが流行した。壁画の中には,死者の生前の生活風景を描画したもののほかに,その昇天する様子を描いたと思われる画像が確認される。被葬者が天界の(3)神のもとへ無事行き着けるよう願って,遺族がこのような装飾を墓に施したのであろう。
問1 下線部(1)に関連して,世界史上における法律について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】
- (1)洪武帝によって,明律が制定された。
- (2)東ローマ帝国で,『ローマ法大全』が編纂された。
- (3)インドで,『マヌ法典』がまとめられた。
- (4)ギリシアで,ホルテンシウス法が制定された。
問2 下線部(2)に関連して,中国で主に副葬品として墓中に納められた焼き物で,ラクダの上に西域人が乗っている次の写真の陶器の呼称として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

【写真1】
- (1)彩 陶
- (2)唐三彩
- (3)染付(青花)
- (4)黒 陶
問3 下線部(3)について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】
- オシリス神は,古代エジプトにおいて冥界の王とみなされていた。
- シヴァ神は,ヒンドゥー教の主神の一つである。
- (1)a ― 正 b ― 正
- (2)a ― 正 b ― 誤
- (3)a ― 誤 b ― 正
- (4)a ― 誤 b ― 誤
B 宗教の開祖,指導者,殉教者らの(4)墓は,巡礼や参詣の対象となることが多い。イスラーム教では,12世紀以降,多くのスーフィー教団(イスラーム神秘主義教団)が結成されたが,その核となった著名なスーフィー聖者たちの墓廟も重要な参詣対象となっている。例えば,(5)トルコのコンヤにあるメヴレヴィー教団の開祖ルーミーの墓廟には,今日でも参詣者が絶えない。一方,18世紀の【ア】では,【イ】がイスラーム改革運動を起こし,聖者への崇敬は預言者ムハンマドの時代にはなかったとして,豪族サウード家と結んで聖者などの墓廟を破壊していった。
問4 文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】
- (1)ア ― エジプト イ ― ワフド党
- (2)ア ― エジプト イ ― ワッハーブ派
- (3)ア ― アラビア半島 イ ― ワフド党
- (4)ア ― アラビア半島 イ ― ワッハーブ派
問5 下線部(4)について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】
a 始皇帝の陵墓近くから,兵馬俑が発掘された。
b 古代ローマのカタコンベは,キリスト教徒の礼拝の場ともなった。
- (1)a ― 正 b ― 正
- (2)a ― 正 b ― 誤
- (3)a ― 誤 b ― 正
- (4)a ― 誤 b ― 誤
問6 下線部(5)に関連して,トルコ系の国家や王朝について述べた文として波線部の誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】
- (1)突厥が,ササン朝と結んでエフタルを滅ぼした。
- (2)ウイグルが,キルギスを滅ぼした。
- (3)カラ=ハン朝が,サーマーン朝を滅ぼした。
- (4)ホラズム朝(ホラズム=シャー朝)が,モンゴルに滅ぼされた。
C 死後の世界に天国と地獄が存在するという考えは,歴史上多くの宗教に確認される。中世ヨーロッパにおいても,これら死後の世界のイメージは(6)
「最後の審判」の思想と結びつく形で人々の想像力を強く規定するものとなる。12世紀後半には天国と地獄の間に,罪の
贖いの場として
煉獄が存在するという考えが登場するが,(7)
ダンテは『神曲』でそうした死後世界の様子を詳細に記述してみせた。また天国と地獄をめぐる図像表現は,教会の扉口彫刻やステンドグラスに繰り返し採用され,これらを目にした信徒たちは死への恐れと救済への願望を新たにしたのである。中世末期から(8)
ルネサンスの時代にかけては,著名な画家たちもこの主題に取り組み,数多くの傑作が残されている(下図参照)。
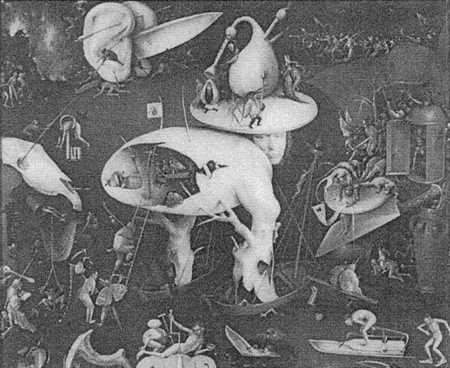
【写真2】
ヒエロニムス=ボスによる地獄の表現
問7 下線部(6)に関連して,キリスト教におけるこの思想の形成に大きな影響を与えた宗教として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】
- (1)道教
- (2)ゾロアスター教
- (3)バラモン教
- (4)イスラーム教
問8 下線部(7)の人物の出身地であるフィレンツェについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】
- (1)毛織物業で,富を蓄積した。
- (2)14世紀には,教皇庁が置かれた。
- (3)フッガー家の庇護の下,芸術が栄えた。
- (4)ブルネレスキが,ハギア=ソフィア(聖ソフィア)聖堂を建てた。
問9 下線部(8)の時期の文学について述べた次の文a~cが,年代の古いものから順に正しく配列されているものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【9】
a エラスムスが,『愚神礼讃』を書いた。
b ペトラルカが,叙情詩を作った。
c セルバンテスが,『ドン=キホーテ』を著した。
- (1)a → b → c
- (2)a → c → b
- (3)b → a → c
- (4)b → c → a
- (5)c → a → b
- (6)c → b → a
第2問 世界史上の国境について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)
A 16世紀半ばにカザン=ハン国を攻略したことをきっかけとして,ロシアはヴォルガ川を越えて東方への領土の拡大を本格的に開始した。ロシアの商人やコサックは毛皮を求めて(1)シベリアを横断し,やがてオホーツク海に到達した。領土拡大に伴って,ロシアには清朝と勢力範囲を調整する必要性が生じ,1727年に結ばれた【ア】でモンゴル北辺における露清間の国境が定められた。
(2)日本との間では樺太(サハリン)や千島列島が係争の対象となり,両国は1855年に日露和親条約を締結するに至った。
問1 【ア】に入れる条約の名と,当時の清朝の皇帝の名との組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】
- (1)南京条約 ― 康熙帝
- (2)南京条約 ― 雍正帝
- (3)キャフタ条約 ― 康熙帝
- (4)キャフタ条約 ― 雍正帝
問2 下線部(1)の地域について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】
- (1)イヴァン4世の治世下で,イェルマークのシベリア遠征が行われた。
- (2)日本は,シベリア出兵(対ソ干渉戦争)に参加した。
- (3) 20世紀前半に,シベリア鉄道の建設が始まった。
- (4)19世紀に,ムラヴィヨフが東シベリア総督となった。
問3 下線部(2)に関連して,日本とロシアの関係の歴史について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】
- (1)アレクサンドル1世が,ラクスマンを日本に派遣した。
- (2)日露戦争の結果,日本は樺太全島を領有するようになった。
- (3)日ソ中立条約が結ばれた後,第二次世界大戦が始まった。
- (4)日ソ共同宣言が出された後,日本は国際連合に加盟した。
B 第一次世界大戦を境に,ヨーロッパの政治地図は大きく塗り替えられることとなった。中・東欧,バルト海地域,バルカン半島では,民族自決の原則を建前として(3)ポーランドをはじめ多くの国家が成立する一方,それまでの諸帝国は解体した。例えば(4)ドイツは,1919年6月に結んだヴェルサイユ条約によって,広大な領土を失った。こうして大戦後のヨーロッパでは,多くの新たな(5)国境線が引かれたのである。だが,これらの地域に曲がりなりにも適用された民族自決の理念は,他地域,とりわけアジア・アフリカにおいて直ちに実現されることはなかった。
問4 下線部(3)の国の歴史について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】
- 社会主義体制下で,自主管理労組「連帯」が結成された。
- チャウシェスクによる独裁体制が崩壊した。
- (1)a ― 正 b ― 正
- (2)a ― 正 b ― 誤
- (3)a ― 誤 b ― 正
- (4)a ― 誤 b ― 誤
問5 下線部(4)の国の歴史について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】
- (1)第二次世界大戦後,米・英・仏・ソ4か国によって分割占領された。
- (2)西ドイツは,ワルシャワ条約機構の一員となった。
- (3)東ドイツは,東西ベルリンの境界に壁を建設した。
- (4)ニュルンベルク国際軍事裁判によって,ナチス=ドイツの指導者が裁かれた。
問6 下線部(5)に関連して,国境の変更や領土の帰属をめぐる歴史について述べた文として波線部の正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】
- (1)アルザス・ロレーヌは,ウィーン会議の結果,ドイツ帝国領となった。
- (2)百年戦争の結果,イギリス王は,ボルドー以外の大陸の所領を失った。
- (3)テキサスは,アメリカ=メキシコ戦争の結果,アメリカ領となった。
- (4)バルト3国は,第二次世界大戦が始まると,ソ連によって併合された。
C 19世紀後半,イギリスとフランスが東南アジア大陸部に勢力を拡大していくなかで,清朝との(6)国境をどのように設定するかが問題になった。それまで清朝は,ヴェトナム・ラオス・ビルマを(7)朝貢国とみなし,自国の領域とこれら朝貢国との間に位置する山岳地域については,現地首長を通じて間接的に(8)統治する政策を採っていた。しかし,イギリスがビルマを植民地化し,フランスがヴェトナムやラオスを支配していく過程で,こうした山岳地域に清朝との国境が定められていった。
問7 下線部(6)に関連して,次の年表に示したa~dの時期のうち,国境を接する中華人民共和国とヴェトナムとの間で起こった中越戦争の時期として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】
【a】
1962年 中印国境紛争
【b】
1969年 中ソ国境紛争
【c】
1975年 ヴェトナム戦争終結
【d】
(1) a (2) b (3) c (4) d
問8 下線部(7)について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】
- 琉球は島津氏に支配されると,中国への朝貢を断絶した。
- 3世紀に卑弥呼が,魏に朝貢使節を送った。
- (1)a ― 正 b ― 正
- (2)a ― 正 b ― 誤
- (3)a ― 誤 b ― 正
- (4)a ― 誤 b ― 誤
問9 下線部(8)に関連して,清朝が設置した機関として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】
- (1)軍機処
- (2)中書省
- (3)理藩院
- (4)総理各国事務衙門(総理衙門)
第3問 世界史上の経済政策について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)
A 漢では,当初,郡県制と封建制を併用する郡国制が施行され,封建された諸侯王は領域内の政治や経済に大きな権限を持った。漢は徐々に諸侯王の権力を削減する政策を採ったが,それに対して,領域内で銅山開発や海塩生産を行い大きな経済力を持っていた呉王が中心となって反乱を起こした。この反乱は結局平定され,その後は,郡県制と変わらない中央集権体制が確立された。(1)前2世紀後半になると,対外積極政策を採る武帝は,北アジアの匈奴を攻撃し,西域に勢力を拡大し,また朝鮮半島北部や(2)ヴェトナム北部にまで進出した。しかしながら,度重なる戦争は財政を圧迫したため,(3)新たな経済政策を打ち出して難局を乗り切ろうとしたが,うまくいかなかった。
問1 下線部(1)の時期に起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】
- (1)張騫が,大月氏に派遣された。
- (2)仏図澄が,仏教の布教に活躍した。
- (3)耶律大石が,西遼(カラ=キタイ)を建てた。
- (4)班超が,西域都護となった。
問2 下線部(2)の地域に建国され交易で栄えた国の名として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】
- (1)マタラム
- (2)チャンパー(林邑)
- (3)パルティア
- (4)カルタゴ
問3 下線部(3)に関連して,漢の武帝の時代の経済政策について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】
- (1)中小商人への低利の貸付である市易法を施行した。
- (2)土地政策として均田制を施行した。
- (3)物価対策などのために均輸・平準法を施行した。
- (4)貨幣を半両銭に統一した。
B 16世紀は,銀が大量に流通し,東アジアとヨーロッパが銀を介して結びついていった時代である。16世紀前半,まず東アジアにおける銀の流通に大きく作用したのは,日本の石見銀山などで産出された銀であった。この銀の動きには,インド洋を経由して東アジアに到達した(4)ポルトガルが大きくかかわっていた。16世紀後半になると(5)アメリカ大陸で産出された銀が中国に流入し始める。すなわち,スペインがアメリカ大陸の銀を,太平洋を経由してフィリピンの交易拠点にもたらし,これが中国へ流入していったのである。このような銀の流れは,中国やヨーロッパ諸国の(6)経済政策に大きな影響を与えた。
問4 下線部(4)の国が交易の拠点とした都市の名と,その位置を示す次の地図中のaまたはbとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】
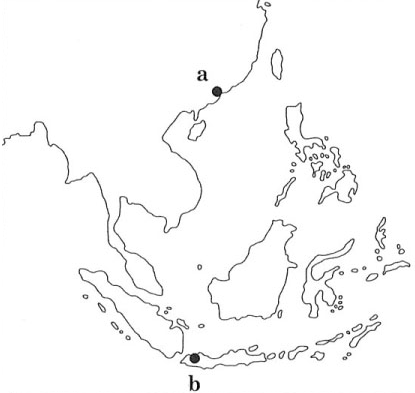
【地図1】
- (1)バタヴィア ― a
- (2)バタヴィア ― b
- (3)マカオ ― a
- (4)マカオ ― b
問5 下線部(5)に関連して,16世紀にアメリカ大陸で大量の銀を産出した鉱山の名として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】
- (1)クスコ
- (2)ポトシ
- (3)アンボイナ(アンボン)
- (4)ゴア
問6 下線部(6)に関連して,中国の税制のうち次のa~cが,導入された時期の古いものから順に正しく配列されているものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【24】
- 地丁銀制
- 両税法
- 一条鞭法
- (1)a → b → c
- (2)a → c → b
- (3)b → a → c
- (4)b → c → a
- (5)c → a → b
- (6)c → b → a
C ヨーロッパでは19世紀半ばまでに,イギリスを中心とする自由貿易体制が確立されるとともに,自由放任主義が各国に浸透した。だが,1870年代に発生した「大不況」の結果,各国で(7)保護関税政策が台頭し,自由貿易体制は崩れた。また,ドイツで(8)ビスマルクが世界に先駆けて制度化した一連の社会保険は,それまで自助原則にゆだねられていたライフサイクル上の様々なリスクを軽減させた一方で,人々の生活に対する国家の介入を招いた。そして,このような国家的介入は,(9)第一次世界大戦中の総力戦体制によって本格的に展開することとなる。
問7 下線部(7)に関連して,世界史上の関税について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】
- 清は黄埔条約によって,イギリスに対する関税自主権を失った。
- イギリスは穀物法によって,輸入穀物に対する関税を撤廃した。
- (1)a ― 正 b ― 正
- (2)a ― 正 b ― 誤
- (3)a ― 誤 b ― 正
- (4)a ― 誤 b ― 誤
問8 下線部(8)の人物の事績について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】
- (1)ロシアと再保障条約を結んだ。
- (2)フランクフルト国民議会を開いた。
- (3)ユダヤ人に対する文化闘争を展開させた。
- (4)積極的な海外進出を目指す「世界政策」を打ち出した。
問9 下線部(9)の時期に起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】
- (1)フランスで,「平和に関する布告」が出された。
- (2)ドイツ領南洋諸島が,日本によって占領された。
- (3)イタリアのキール軍港で,水兵が反乱を起こした。
- (4)中国で,共産党が結成された。
第4問 世界史上の言語について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)
A 話し言葉に基づいて書き言葉を創出すること,すなわち言文一致は国民統合の重要な課題とされた。言文一致は,近代日本だけでなく,中国や朝鮮でも試みられた。例えば,朝鮮では旧来,エリート層の学ぶ漢文が公式の書き言葉とされ,大多数の民衆はその世界から排除されていた。しかし,(1)19世紀末に朝鮮政府は,民衆世界に普及していた(2)固有の文字ハングルと朝鮮語を公用文に採用することを決定し,朝鮮語の書き言葉の形成を推進した。言文一致の条件はこのようにして整備されたのである。言文一致体は(3)近代的知識を広める重要な媒体とも考えられ,このような動きは,日本統治期には危険視された。
問1 下線部(1)の時期に起こった出来事として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】
- (1)日本は,台湾出兵を行った。
- (2)インド国民会議が結成された。
- (3)ドイツは,オーストリア・イタリアと三国同盟を結んだ。
- (4)韓国(大韓帝国)は,日本と日韓協約を締結した。
問2 下線部(2)に関連して,アジアにおける固有の文字の形成について述べた次の文a~cが,年代の古いものから順に正しく配列されているものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【29】
- 朝鮮(李朝)では,訓民正音(ハングル)が作られた。
- 遼では,契丹文字が作られた。
- ヴェトナム(陳朝)では,字喃(チュノム)が作られた。
- (1)a → b → c
- (2)a → c → b
- (3)b → a → c
- (4)b → c → a
- (5)c → a → b
- (6)c → b → a
問3 下線部(3)に関連して,1910年代における中国・朝鮮の言文一致と啓蒙運動について述べた次の文章中の【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】
中国で胡適や魯迅などによって推進された白話(白話文学)運動は,知識や思想の革新を主張する【ア】を進展させた。しかし,朝鮮では【イ】によって,このような啓蒙運動の展開が著しく制限された。
- (1)ア ― 文化大革命 イ ― 武断政治(武断統治)
- (2)ア ― 文化大革命 イ ― 羈縻政策
- (3)ア ― 新文化運動 イ ― 武断政治(武断統治)
- (4)ア ― 新文化運動 イ ― 羈縻政策
B 古来,(4)南アジアには,様々な人種・民族が到来するのに伴い,多様な言語がもたらされた。それらは,併存しつつ互いに影響を与え合うことで,複雑な言語状況を作り上げた。現在,南アジアの諸言語は,【ア】などのドラヴィダ系,【イ】などのインド=ヨーロッパ系,さらにアウストロアジア系,シナ=チベット系に分類されるのが通例である。19世紀以降の言語をめぐる問題は,こうした複雑さを反映し,しばしば激しい対立に至った。(5)1950年1月に施行されたインド憲法は,連邦レベルの公用語を定めるとともに,特に重要なものとして14もの言語を認めざるを得なかった。
問4 文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】
- (1)ア ― ヒンディー語 イ ― タミル語
- (2)ア ― ヒンディー語 イ ― アッカド語
- (3)ア ― タミル語 イ ― ヒンディー語
- (4)ア ― アッカド語 イ ― ヒンディー語
問5 下線部(4)の地域の言語について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】
a インダス文字は,20世紀に解読された。
b ムガル帝国では,ペルシア語が公用語(公式文書に用いられる言語)であった。
- (1)a ― 正 b ― 正
- (2)a ― 正 b ― 誤
- (3)a ― 誤 b ― 正
- (4)a ― 誤 b ― 誤
問6 下線部(5)に関連して,1950年代に起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】
- (1)インドとパキスタンが,相次いで核実験を行った。
- (2)ハンガリーで,反ソ暴動(ハンガリー事件)が起こった。
- (3)中華人民共和国が,国連における代表権を獲得した。
- (4)ソ連が,キューバにミサイルを配備した。
C (6)ヨーロッパでは19世紀以降,言語を一つの核とする(7)ナショナリズムが高まる。南部アフリカでも,南アフリカ戦争(ボーア戦争)の前後には,オランダ系入植者の子孫がその話し言葉を,書き言葉之アフリカーンス語として確立していった。アフリカーンス語は1920年代には,英語と並ぶ南アフリカの公用語となる。しかし,アパルトヘイト政策が本格化すると圧制者の言語のイメージが強まり,1976年には,(8)アフリカ人などがアフリカーンス語での教育に反対し,ソウェト蜂起を起こした。アパルトヘイトが終わった今日,英語が共通語であり続けているのに対して,アフリカーンス語の地位は大幅に低下している。
問7 下線部(6)の言語の歴史について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】
- ギリシア人は,異民族をバルバロイ(聞き苦しい,訳の分からないことばを話す者)と呼んだ。
- ルターは,神聖ローマ皇帝の保護の下で,『新約聖書』をドイツ語に翻訳した。
- (1)a ― 正 b ― 正
- (2)a ― 正 b ― 誤
- (3)a ― 誤 b ― 正
- (4)a ― 誤 b ― 誤
問8 下線部(7)に関連して,「未回収のイタリア」に含まれる地域の名と,その位置を示す次の地図中のaまたはbとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】
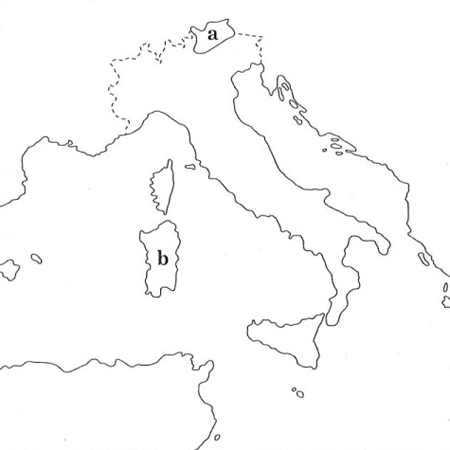
- (1)南チロル(南ティロル) ― a
- (2)南チロル(南ティロル) ― b
- (3)トリエステ ― a
- (4)トリエステ ― b
問9 下線部(8)の地域の歴史について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】
- (1)ザンベジ川の南では,アクスム王国が栄えた。
- (2)西アフリカから大西洋を越えて,奴隷が輸出された。
- (3)1970年は,「アフリカの年」と呼ばれた。
- (4)アフリカ連合(AU)は,アフリカ統一機構(OAU)に発展した。