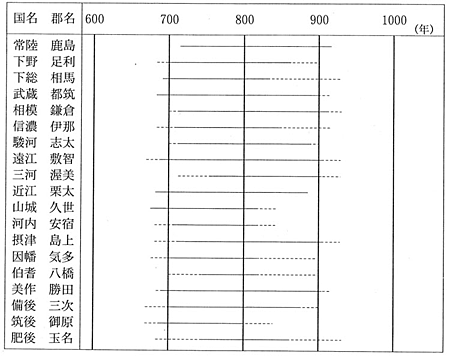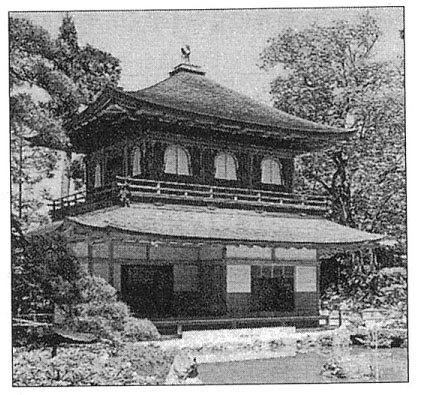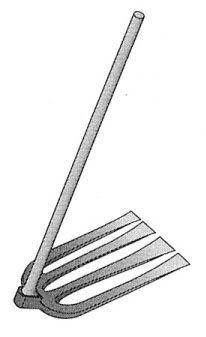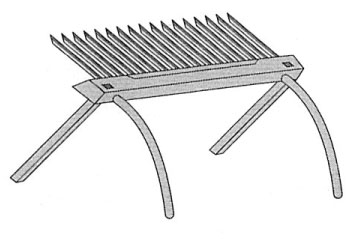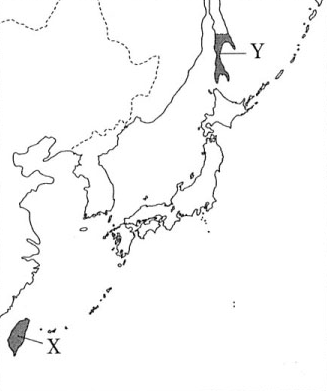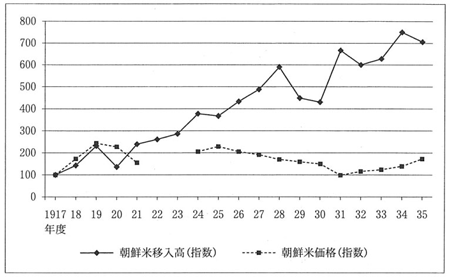2012年度 センター試験【日本史B】問題
(解答番号【1】~【36】)
第1問 次の文章A・Bは,高校生の拓也さんと歴史博物館で働いている姉の美咲さんとの会話である。この文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 12)
A
拓 也:修学旅行で,最近築城400年を迎えたお城に行ってきたよ。お城の横の博物館で,本にも載っている有名な屏風が展示されていたな。
美 咲:屏風には長い歴史があるし,部屋を仕切る実用性だけではなくて,装飾品としての美しさもあるわ。(a)屏風に描かれている絵から,当時の生活文化などの情報を読み取ることもできるのよ。
拓 也:実物を見てはじめてわかったけど,あの屏風には楽器を演奏している人も描かれているんだね。(b)昔の楽器や歌って,どんな音色やメロディーだったのか,聴いてみたいな。
美 咲:そうね。音の復元研究をして,博物館の展示に活かせるといいわね。
拓 也:そういえば,僕が行った博物館では,陶器作りの様子を記録した映像を上映していたよ。もの作りの技術も,文化財なんだってね。
美 咲:そう,昔の生活で使われてきた民具や,地域に伝わるお祭りも文化財なのよ。でも,こういう生活に密着した文化は,大切なものだと理解されていないと壊されたり,捨てられたり,すたれてしまったりする危険があるの。
拓 也:そうか。だから,(c)博物館や資料館などでは,しっかりと保存したり記録をとったりして,文化財を守っていかなくちゃいけないんだね。姉さんたちがどんな仕事をしているのか,ようやくわかってきたよ。姉さんが,いつも忙しくしているわけだ。
問1 下線部(a)に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】
- (1)正倉院に伝わる鳥毛立女屏風は,宋の文化の影響をうけている。
- (2)平安貴族の住宅では,金地に緑・青などを使う濃絵の屏風が使われた。
- (3)南蛮人との交流を通して,その風俗が屏風に描かれるようになった。
- (4)江戸幕府の御用絵師たちが,屏風に豪華な錦絵を描いた。
問2 下線部(b)に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】
- 鎌倉時代には,平曲の伴奏に三味線が使われた。
- 江戸時代には,人形浄瑠璃の伴奏に三味線が使われた。
- 明治時代には,西洋音楽をもとにした唱歌が学校教育に用いられた。
- 明治時代には,ラジオ放送やレコードの普及によって流行歌が生まれた。
(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d
問3 下線部(c)に関連して,文化財の保護や保存に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【3】
Ⅰ 法隆寺金堂壁画が焼損したことを契機に,文化財保護法が制定された。
Ⅱ 原爆の惨禍を伝える原爆ドームが,全人類の文化遺産として,世界遺産に登録された。
Ⅲ フェノロサが,日本の伝統美術の保存と復興を説いた。
(1) Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ (2) Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ (3) Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ
(4) Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ (5) Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ (6) Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ
B
拓 也:お城の中もいろいろ見てまわったよ。複雑な郭や高層の【ア】をもつ,城郭建築がよく理解できたな。
美 咲:うちの近所にも,戦国時代に地元の領主が造ったお城があったのよ。
拓 也:へえ,戦国時代のお城って大名だけが造るものだと思っていた。
美 咲:ここのお城は石垣がなくて,堀や【イ】のような防御施設に囲まれていたのね。あのあたりに,今でも城ノ内,堀ノ内という地名があるでしょう。廃城になってしまったけれど,(d)ここにお城があったということが,地名からわかるのよ。
拓 也:地名も一種の文化財なんだね。景観からも歴史がわかるのかな。
美 咲:そうね,たとえば江戸時代の城下町の道は,大名が造らせた道路だから,防御のために,わざと曲げたりしているわ。それから,私が勤めいる博物館の前の道路も,まっすぐで幅が広いでしょう。昔あそこに何があったか,知っているかしら。
拓 也:飛行場があったって,学校で聞いたよ。
美 咲:戦争中,陸軍がパイロットを養成していたの。あの道路は滑走路だったのよ。ここの地域の人たちなどを動員して造られた滑走路が,道路に形を変えて今でも(e)戦争遺跡として残っているわけ。
拓 也:僕たちの身近にあるものからも,歴史や文化を学ぶことができるんだね。
美 咲:そうそう。だから私たちは,法律や条例で指定されたもの以外にも文化財があるんだって,みんなに知ってもらいたいと思っているの。こうした,いろんな文化財の保存と活用のためにも,地域の人たちと一緒にもっと考えていきたいわね。
問4 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】
(1) ア 天守閣 イ 墳 丘 (2) ア 天守閣 イ 土 塁
(3) ア 堂 塔 イ 墳 丘 (4) ア 堂 塔 イ 土 塁
問5 下線部(d)に関連して,地名にかかわる歴史について述べた次の文X・Yと,それに最も関係の深い地名a~dの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】
X 江戸時代には,米の増産をはかるために,商人資本を活用して開発が行われた。
Y 江戸時代の街道には,宿駅や関所などの施設が設けられた。
a 銀 座 b 新 田) c 大 湊 d 一里塚
(1) X-a Y-c (2) X-a Y-d
(3) X-b Y-c (4) X-b Y-d
問6 下線部(e)に関連して,戦争・軍事に関する遺跡について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】
- (1)白村江の戦い以後の朝鮮半島情勢を意識した防衛策として,奈良盆地に水城が築かれた。
- (2)島原・天草一揆(島原の乱)で,一揆勢は原城跡に立てこもった。
- (3)幕末には,海防を強化するため,江戸湾に台場が築かれた。
- (4)一般住民が集団自決に追い込まれた沖縄では,多くの戦跡が平和を考える場となっている。
第2問 古代の政治・社会・文化に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 18)
A 中国にならって成立した律令国家は,
精緻に組み立てられた官僚制や租税制度などを特徴としていた。ただ,その実態は,日本の社会の実情にあわせたものとなっており,中国とはさまざまな点で異なっていた。
地方支配の仕組みをみると,中央の官人が国司として派遣され,国府の下級官人を率いて一国内を統治する一方,(a)
郡には郡司や里長がおかれ,独自の役割が期待されていた。また民衆は,中国と同様,戸籍に登録されることによって一人一人が中央政府に把握されたが,(b)
そこでの戸は,実際の家族そのままではなく,平均20数名になるよう,帳簿の上で編成し直したものであったと考えられている。
こうした国家体制のもと,民衆は厳しい税の取立てに苦しんだ。(c)
次の史料は,そうした民衆の生活の様子を詠んだ歌である。
…… かまどには
火気吹き立てず

(注1)には
蜘蛛の巣かきて
飯炊くことも忘れて ぬえ鳥の のどよひ居るに(注2) いとのきて(注3) 短き物を
端切ると 言へるがごとく しもと(注4)取る
五十戸良(注5)が声は
寝屋処まで 来立ち呼ばひぬ ……
(『万葉集』巻第5)
(注1)

:米や豆などを蒸すための器。
(注2) のどよひ居るに:細い力のない声を出していると。その前の「ぬえ鳥の」は「のどよひ居るに」にかかる枕詞。
(注3) いとのきて:とりわけ
(注4) しもと:むち
(注5) 五十戸良:里長
問1 下線部(a)に関連して,5~8世紀の地方支配について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】
- (1)ヤマト政権はそれまでの地方豪族を没落させ,中央から国造を派遣して地方を支配した。
- (2)郡司は,もとの国造など地方豪族のなかから選ばれた。
- (3)国造のなかには,大王家に直属する初期荘園の管理を行う者もいた。
- (4)郡司のなかには,出羽の磐井のように反乱を起こす者もいた。
問2 下線部(b)に関連して,奈良時代の戸籍や民衆の生活について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】
- (1)律令国家は,原則として6年ごとに戸籍を作成した。
- (2)律令国家は民衆に対し,戸籍にもとづいて口分田を班給した。
- (3)結婚のかたちの一つとして,男性が女性の家に通う妻問婚があった。
- (4)民衆は,木綿の衣類を着るようになった。
問3 下線部(c)に関連して,この史料や,そこからうかがえることに関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】
- この歌は,山上憶良が作ったものである。
- この歌は,東国の民衆が作ったものである。
- この歌が作られたころの国司は,郡司や里長を通じて徴税を行っていた。
- この歌が作られたころの国司は,在庁官人を通じて徴税を行っていた。
(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d
B 平安時代に入ると,中央政府のなかで,中国の姿に近づこうとする動きがさらに強まった。9世紀前半の嵯峨天皇のころには,文芸によって国家の隆盛をめざそうとする中国の思想が広まり,【ア】などの勅撰漢詩文集が編まれた。このころ,律令制定後に出された法令を分類・編集して最初の【イ】が編まれたが,律令と【イ】をあわせもつこともまた,中国にならったことであった。
だが地方社会では,すでに律令体制の根幹がくずれはじめていた。たとえば,浮浪したり逃亡したりする者や,課税を逃れようとする偽籍も多くなっていた。やがて(d)郡司が政務を行う郡家(郡衙)のあり方にも変化が生じ,郡司の役割が変化したことをうかがわせる。
こうした状況のなか,10世紀になると,中央政府は従来の地方支配のやり方を転換し,国司の権限も大きくなっていった。ちょうどこのころには,日本が手本とした中国などでも大きな変化が起こっており,(e)東アジア諸国は変動の時期に入っていた。
問4 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】
(1) ア 凌雲集 イ 国 史 (2) ア 凌雲集 イ 格 式
(3) ア 風土記 イ 国 史 (4) ア 風土記 イ 格 式
問5 下線部(d)に関連して,遺跡からみた郡家(郡衙)の存続期間を示した次の表から推定されることを述べた下の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】
遺跡からみた郡家(郡衙)の存続期間
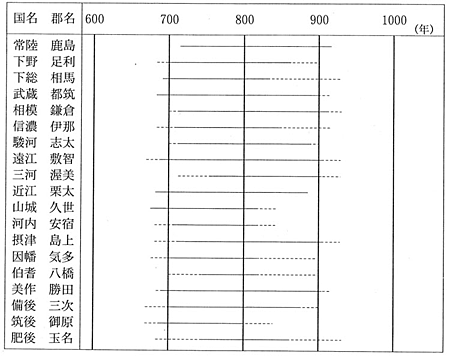
【表1】
(山中敏史『古代地方官衙遺跡の研究』より作成)
(注) 破線は,遺跡の存在が不確かな期間。
X ほとんどの郡家(郡衙)は乙巳の変の前に成立していた。
Y 8~9世紀にあった郡家(郡衙)は,10世紀後半ころにはほとんどが衰退・消滅していた。
(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤
(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤
問6 下線部(e)に関して述べた次の文X・Yと,それに該当する国名a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】
X 日本の律令国家のモデルとなったこの国は,10世紀初めに滅亡した。
Y 奈良時代以来,日本と親交のあった北東アジアのこの国は,10世紀前半に遼(契丹)によって滅ぼされた。
a 唐 b 宋 c 渤 海 d 百 済
(1) X-a Y-c (2) X-a Y-d
(3) X-b Y-c (4) X-b Y-d
第3問 中世の政治に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 18)
A 12世紀末に鎌倉幕府が成立したが,幕府内での権力のあり方は,鎌倉時代を通じて一様であったわけではない。その変化の流れを追ってみよう。
はじめは,武家政権の長である鎌倉殿(将軍)が侍所・政所などを統轄して,専制的な権力をふるった。初代将軍頼朝の妻政子も,3代将軍【ア】の暗殺後は事実上の鎌倉殿であったといわれる。その様子は,幕府の歴史を編年体で編纂した『【イ】』にいきいきと描かれており,承久の乱にあたって,政子は御家人らの前で頼朝の恩顧を述べ結束をよびかけたと記されている。
その後,幕府政治は執権北条氏を中心としながら,有力な御家人らの合議にもとづき政権を運営する段階へと移り,この時期には(a)御成敗式目の制定など法の整備も進められた。
(b)鎌倉時代の後半になると,北条氏嫡流の当主である得宗が幕府の権力を握った。このころから,重要事項を決定する会議が得宗の私邸で行われるようになり,参加者は得宗とその近臣などに限られるようになった。
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】
(1) ア 頼 家 イ 吾妻鏡 (2) ア 頼 家 イ 愚管抄
(3) ア 実 朝 イ 吾妻鏡 (4) ア 実 朝 イ 愚管抄
問2 下線部(a)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】
X 頼朝以来の先例や,当時の武士たちの間で重視されていた道理にもとづいて制定された。
Y 律令や公家法を否定すべきものとして制定された。
(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤
(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤
問3 下線部(b)に関連して,このころの人々の活動について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】
- (1)幕府や荘園領主の支配に抵抗する者が,悪党とよばれた。
- (2)足軽が鉄砲隊に組織され,活躍した。
- (3)都市鎌倉では,大原女などの女性商人が活躍した。
- (4)交通の要所では,商品の中継ぎや運送を行う借上が現れた。
B 室町時代には,足利氏の当主が武家政権の長となった。3代将軍義満のもとで,約60年にわたった南北朝の動乱がおさまり,幕府機構の整備も進んだ。義満は有力な守護大名への攻勢を強め,権力の集中をはかり,将軍を退いたあとも,武家のみならず公家社会に対しても強い権力をふるった。その際,(c)明との外交が義満の権力に与えた影響は見逃せない。
4代将軍義持の時代には,将軍と有力守護との間で勢力の均衡が保たれていたが,6代将軍義教は専制を強め,「万人恐怖」といわれる政治を行った。そのため,彼がついに播磨の守護赤松満祐によって暗殺されると,「自業自得」の結果とも評され,将軍権力は弱体化していった。
(d)8代将軍義政は,一時期,父の義教にならって専制志向をみせるが,守護大名たちの抵抗にあって失敗してからは,政治に対して消極的になった。応仁の乱が起こると,将軍や幕府の求心力はさらに低下し,(e)戦国の世が到来した。
問4 下線部(c)に関連して,14世紀から15世紀にかけての日明関係に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【16】
Ⅰ 足利義持によって,明との貿易が一時中止された。
Ⅱ 九州の懐良親王に,明が倭寇の取締りを要求した。
Ⅲ 明皇帝が,「源道義」を「日本国王」とした。
(1) Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ (2) Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ (3) Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ
(4) Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ (5) Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ (6) Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ
問5 下線部(d)に関連して,この人物が造営した次の写真の建造物について述べた文として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】
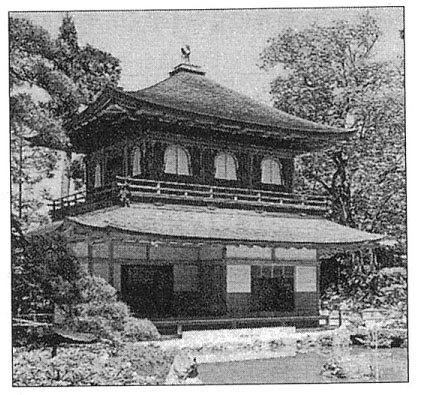
【写真1】
- (1)京都の北山に造られた。
- (2)浄土真宗の影響が色濃くみられる。
- (3)下層は書院造の代表的建築である。
- (4)上層には長谷川等伯の描いた障壁画がある。
問6 下線部(e)に関連して,15世紀後半から16世紀に起きた戦乱について述べた文として誤っているものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】
- (1)加賀の一向一揆が,守護の富樫政親を倒した。
- (2)北条氏康が,堀越公方を滅ぼした。
- (3)毛利元就が,陶晴賢を滅ぼした。
- (4)織田信長が,桶狭間の戦いで今川義元を倒した。
第4問 近世の政治・社会に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 17)
A 近世社会の特徴の一つに農書の登場がある。戦乱の時代の終結によって,(a)生産を拡大しようという人々の意欲が高まるとともに,17世紀を通じて経営規模の小さな百姓の家が多数生まれた。その結果,農業技術を文字によって伝えようとする志向が生まれ,農書が著されるようになった。
興味深いのは,農書は農業技術を伝えるだけでなく,農民としての心構えをも説くものだったことである。たとえば,17世紀後半に成立した『【ア】』や『百姓伝記』では,(b)「仁」や「孝」といった儒学の徳目が重視され,それを実践する農民こそ豊かになれるとする。農書にあらわれている近世農民の姿は,農業耕作をみずからの役割として位置づけるものであった。彼らは,一方的に支配される存在ではなかったといえよう。
しかし,特に『百姓伝記』では,「仁」や「孝」が欠ければ畜類と異ならないとし,乞食や【イ】に転じるとも説いている。それは,【イ】などの(c)賤視された人々への差別意識をともなうという限界をもつものでもあった。
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】
- (1)ア 農業全書 イ 非 人
- (2)ア 農業全書 イ 日 用
- (3)ア 広益国産考 イ 非 人
- (4)ア 広益国産考 イ 日 用
問2 下線部(a)に関連して,江戸時代に普及した次の農具X・Yと,それについて説明した下の文a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】
X
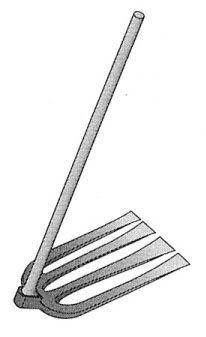
【図1】
Y
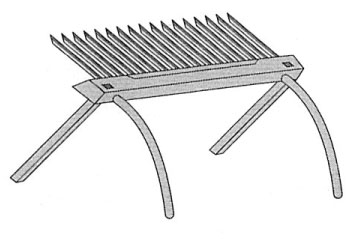
【図2】
a 牛にひかせて土を掘り起こす犂 b 深耕に適した鍬
c 能率的な脱穀用具 d 穀粒の選別用具
(1) X-a Y-c (2) X-a Y-d
(3) X-b Y-c (4) X-b Y-d
問3 下線部(b)に関連して,江戸時代の儒者と対外関係に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【21】
Ⅰ 水戸藩の会沢安(正志斎)が『新論』を書き,尊王攘夷運動に影響を与えた。
Ⅱ 木下順庵の門下である雨森芳洲が,対馬藩で対朝鮮外交に尽力した。
Ⅲ 幕府に登用された林羅山が,外交文書を起草した。
(1) Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ (2) Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ (3) Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ
(4) Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ (5) Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ (6) Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ
問4 下線部(c)に関連して,江戸時代における身分と村社会について述べた文として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】
- (1)入会地や用水の管理など村の運営は,城下町に常駐した武士によって行われた。
- (2)村役人には,苗字・帯刀を許された者でなければ就任できなかった。
- (3)牛馬の死体処理や皮革産業に携わる者が,農業にかかわることはなかった。
- (4)百姓身分のなかには,農業のほか,林業・漁業に従事する者もいた。
B 次の史料は,19世紀前半の随筆『世事見聞録』の一部である。
(d)当世かくの如く貧福偏り勝劣甚だしく出来て,有徳人(注1)一人あればその辺に困窮の百姓二十人も三十人も出来,(中略)百姓の騒動するは,領主・地頭(注2)の責め誣ぐる事のみにはあるべからず。必ずその土地に有余のものあつて大勢の小前(注3)を貪るゆえ,(e)苦痛に迫りて一揆など企つるなり。
(注1) 有徳人:富裕な人。 (注2) 地頭:ここでは,旗本などで領地をもつ人。
(注3) 小前:小百姓のこと。
問5 下線部(d)に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】
- 商品経済の発達とともに,在郷商人の活動がさかんになった。
- 商品経済の発達とともに,札差とよばれる村役人の金融活動がさかんになった。
- 質流れにより,土地を大規模に集積する地主が現れた。
- 質流れにより,領地を集積する旗本・御家人が増えた。
(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d
問6 下線部(e)に関連して,幕末の民衆運動に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】
X 佐倉惣五郎が,年貢減免を求めて将軍徳川家茂に直訴した。
Y 「世直し」を唱える一揆や打ちこわしが起こった。
(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤
(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤
第5問 明治期における日本の領土とその支配に関する次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 12)
近代国家の確立をめざす明治政府は,対外的にはそれまで曖昧だった国境を画定すると同時に,国内では新たな統治の仕組みを整備することを課題とした。
(a)国境の画定については,江戸幕府の支配が十分およんでいなかった日本列島の周縁部が,1870年代にしだいに日本の領土に組み込まれ,支配領域が明確になっていった。さらに1880年代以後,国境を意味する主権線とその外縁部を意味する利益線を外へ広げようとする動きが顕在化する。(b)朝鮮へのあいつぐ軍事介入は,そうした動きを象徴するといえよう。最終的に朝鮮は日本の植民地となり,(c)さまざまな物資が日本本土へ移送される一方で,日本人の移住も本格化した。
画定された国境の内部では,(d)市制・町村制や府県制・郡制などの地方制度が整備されていったが,この制度も北海道や沖縄県,離島などには当初は適用されず,植民地は除外されつづけた。このように国境内部でも統治の諸制度は均一には適用されなかった。また府県知事が官選であるなど国家の統制の強さや,地方行政への住民のかかわり方からみても,戦後の地方自治とは大きく異なっていた。
問1 下線部(a)に関連して,次の地図上の地域X・Yに関して述べた下の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】
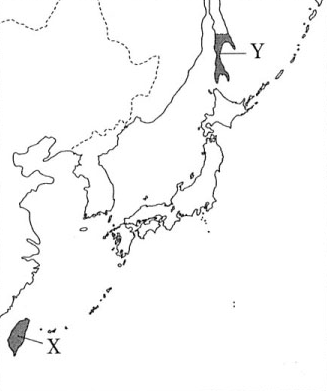
【地図1】
- Xには,琉球の漂流民が殺害された事件を理由に,日本が出兵を行った。
- Xには,日本の植民地となった際,関東都督府が設置された。
- Yは,日露和親条約によってロシアの領土となった。
- Yは,日露戦争の講和条約によって日本の領土となった。
(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d
問2 下線部(b)に関連して,明治期の朝鮮半島をめぐる日本・朝鮮・中国の関係について述べた文として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】
- (1)日本は,征韓論を唱えていた西郷隆盛を朝鮮に派遣し,開国を迫った。
- (2)日本は朝鮮政府と,治外法権を相互に認めるなど,対等な内容の日朝修好条規を結んだ。
- (3)金玉均らは日本公使館の援助のもとにクーデタを起こしたが,清国軍の出動で失敗に終わった。
- (4)朝鮮政府が甲午農民運動のため日本に出兵を依頼すると,清国も対抗して朝鮮に出兵した。
問3 下線部(c)に関連して,大正期から昭和期にかけての朝鮮からの米の移入に関する次のグラフの説明として誤っているものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】
朝鮮米の移入高と価格の推移
(いずれも1917年度を100とする指数)
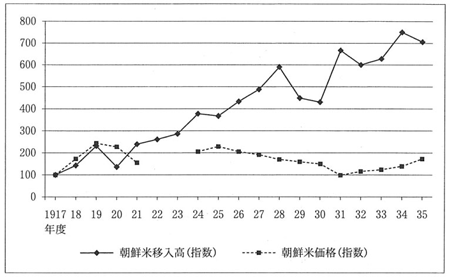
【グラフ1】
(農林省農務局『昭和三年版 米穀統計年報』,農林省米穀局『米穀摘要 昭和十一年九月』より作成)
(注) 価格は東京深川正米市場の1石あたりの玄米(中等米)相場にもとづく月別米価の年度平均。朝鮮米価格の1922・1923年度は不明。
(注) 年度は,前年の11月からその年の10月までの「米穀年度」。
- (1)第一次世界大戦末期には,朝鮮米の価格は上昇した。
- (2)昭和恐慌から立ち直るにつれて,朝鮮米の価格は上昇傾向に転じた。
- (3)1920年代の前半には,朝鮮米の移入高は増加傾向にあった。
- (4)1920年代末には,朝鮮米の移入高が低下し,価格が上昇に転じた。
問4 下線部(d)の制定理由を記した次の史料も参考にしながら,この制度について述べた文として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】
分権の主義に依り行政事務を地方に分任し,国民をして公同(注1)の事務を負担せしめ,以て自治の実を全からしめんとするには,地方の人民をして名誉の為め,無給にして其職を執らしむるを要す。而して之を担任するは其地方人民の義務と為す。力めて多く地方の名望ある者を挙げて此任に当らしむ。
(「市制町村制理由」)
(注1) 公同:公共のこと。
- (1)アメリカ人の法律学者クラークの助言を得て,制定された。
- (2)市町村の行政事務を掌る者には,給与を支払うことが原則とされた。
- (3)市町村の行政事務を担うのは,国民の義務であるとされた。
- (4)市町村の行政事務は,名望にかかわりなく平等に担うこととされた。
第6問 近代日本の代表的な女性運動家であり,のちに政治家としても活躍した市川房枝に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 23)
A 1893年に愛知県で生まれた市川房枝は,新聞記者や労働組合の婦人部書記をつとめるなかで,女性の権利が男性と比べて著しく制限された状態にあると自覚するようになり,1920年,平塚らいてうらと【ア】を結成した。その最初の成果は,1922年,女性の政治集会への参加を禁じていた【イ】第5条の一部改正を実現させたことであった。
市川は,さらに国政への女性の参政権(婦人参政権)を獲得するため,女性団体の結成と運営に尽力した。1930年には,その運動はわずかながら実を結ぶかにみえた。(a)立憲民政党の内閣のもとで,地方参政権に限るなど多くの制約はあったものの,女性に参政権を付与する法案が衆議院で可決されたためである。だがその法案も,貴族院で審議未了のまま廃案となり,戦前の日本では女性の参政権はついに実現しなかった。
問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】
- (1)ア 黎明会 イ 治安警察法
- (2)ア 黎明会 イ 治安維持法
- (3)ア 新婦人協会 イ 治安警察法
- (4)ア 新婦人協会 イ 治安維持法
問2 下線部(a)に関連して,この政党を中心とした内閣が政権を担当していた時期の外交に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】
- 海軍内部の反対意見をおさえて,ロンドン海軍軍縮条約に調印した。
- ワシントン海軍軍縮条約に調印して,協調外交の基礎をつくった。
- 満州事変が起こると,不拡大の方針を決定したが,関東軍による戦線の拡大をおさえられなかった。
- 満州事変を調査したリットン報告書にもとづく国際連盟の勧告を拒否して,連盟を脱退した。
(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d
B (b)1920年代に高まったデモクラシーの思潮や社会運動は,1930年代には思想統制や右翼運動の勃興により苦境に立たされた。市川たちの女性運動も,満州事変では反戦の声をあげて抵抗を示したが,日中戦争が始まると戦争への協力を余議なくされた。市川も,新設された大日本言論報国会理事などの役職に就いた。
(c)戦争が続くなかで食糧などの物資不足が表面化してくると,政府は消費生活を担う銃後の女性の役割に強い関心を払うようになり,女性を大日本国防婦人会などの官製の運動に動員していった。また市川たちの側でも,「かつて自分の時間というものを持ったことのない農村の大衆婦人が,半日家から解放されて講演をきくことだけでも,これは婦人解放である」(『市川房枝自伝 戦前編』)という評価があった。このように,戦前から「婦人解放」を求めていた女性たちの積極性を引き出し,利用するかたちで戦争は進められた。さらに(d)戦争が長期化して労動力不足が深刻化した結果,戦争末期には,女性も生産を担うためのより直接的な戦時動員の対象となっていった。
問3 下線部(b)に関連して,この時期の文化や学問の分野で活躍した人物について述べた次の文X・Yと,それに該当する人物名a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】
X 小説『蟹工船』を著したこの人物は,徳永直らとともにプロレタリア文学の代表的な作家であった。
Y この人物が説いた憲法学説は,1930年代なかばに反国体的として軍部や右翼から排撃された。
a 小林多喜二 b 横光利一 c 美濃部達吉 d 穂積八束
(1) X-a Y-c (2) X-a Y-d
(3) X-b Y-c (4) X-b Y-d
問4 下線部(c)に関連して,この時期の経済政策について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】
- (1)地域社会の生産増強をはかるため,政府は青年団や婦人会を動員して地方改良運動を進めた。
- (2)砂糖やマッチなど生活必需品の購入には,あらかじめ割り当てられた切符が必要となった。
- (3)政府は防穀令を出して,農家から米を強制的に買い上げるようになった。
- (4)経済振興のため,ぜいたく品の消費が奨励された。
問5 下線部(d)に関連して,戦争末期の労働力動員の状況に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】
- 食糧増産を目的にして,沖縄ではひめゆり(学徒)隊が結成された。
- 勤労動員された学生や生徒らが,兵器などの軍需品の生産に従事した。
- 日本本土に連れてこられ,鉱山などで働かされた朝鮮人・中国人もいた。
- 女性を看護要員として召集するために,女子挺身隊が編成された。
(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d
C 敗戦後,GHQが主導する諸改革により,女性の政党加入や参政権が実現し,戦後初の総選挙では多くの女性議員が誕生した。しかし,市川自身は(e)戦時中の役職を理由に公職追放をうけ,解除される1950年まで政治活動が制限された。
1953年,参議院議員になってからは,(f)保守・革新の対立が激しくなる政界のなかで独立した立場を保った。なかでも特徴的なのは,「理想選挙」を唱え,できるだけ資金をかけずに選挙を戦ったことである。市川は戦前から金権政治の風潮を批判しつづけ,(g)戦後も政治資金の流れや疑獄事件を独自に調査して,その政治姿勢を貫いた。そのため,国民にも人気があり,1980年の参議院議員選挙では全国区で第1位当選を果たしたが,翌年,議員在職のまま87歳の生涯を閉じた。
問6 下線部(e)に関連して,占領期の公職追放とその解除について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】
- (1)GHQは,保安条例を発令して軍国主義的な教員を追放させた。
- (2)朝鮮戦争に参戦するため,追放を解除された旧軍人らを中心に保安隊が新設された。
- (3)GHQは,日本共産党幹部の公職追放を指示したが,朝鮮戦争が始まると国内安定のために解除した。
- (4)1950年代には,追放を解除された政治家を首班とする内閣が生まれた。
問7 下線部(f)に関連して,55年体制下の政治について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】
- (1)日米安全保障条約の改定をめざした政権に対して,安保闘争が高揚した。
- (2)サンフランシスコ平和条約の批准をめざして,日本社会党が再統一した。
- (3)1960年代には,民主社会党や公明党が結成され,野党の多党化が進んだ。
- (4)1970年代なかばには,衆議院での与野党の勢力が伯仲した。
問8 下線部(g)に関連して,第二次世界大戦後の疑獄事件に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【36】
Ⅰ 米航空機の売り込みをめぐる収賄容疑により,前首相が逮捕された。
Ⅱ 昭和電工事件が発覚して,片山哲内閣から2代続いた3党連立内閣が倒れた。
Ⅲ 造船疑獄事件をめぐって首相への批判が高まり,戦後初の長期政権が崩壊した。
(1) Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ (2) Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ (3) Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ
(4) Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ (5) Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ (6) Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ

 :米や豆などを蒸すための器。
:米や豆などを蒸すための器。